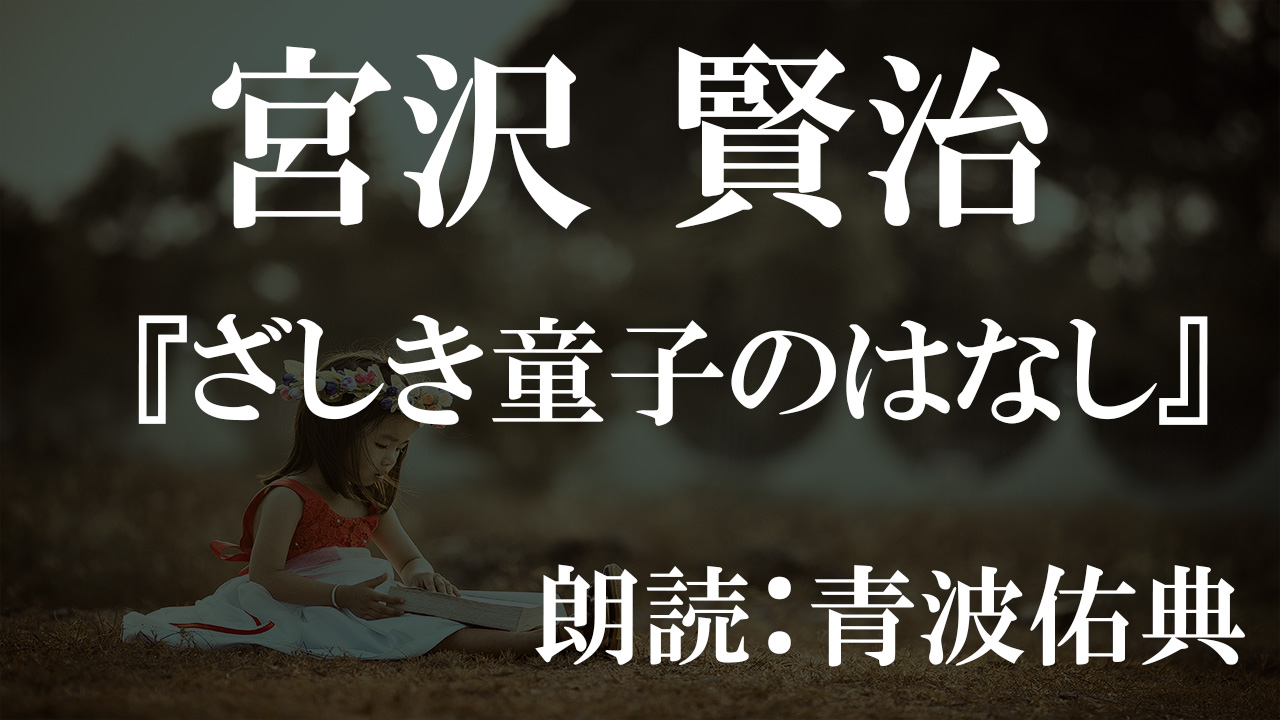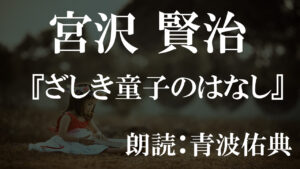東北の民間伝承「ざしき童子」を題材にした宮沢賢治の幻想的短編。
誰もいない座敷から聞こえる箒の音、子供たちの輪に紛れ込む不思議な存在、そして排除されて泣く童子の姿に込められた深いメッセージとは?
目に見えないものへの畏敬と異質なものへの寛容さを問いかける賢治の優しくも哀しい物語世界へ、一緒に耳を澄ませてみませんか?
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『ざしき童子のはなし』の物語概要とあらすじ
- 『ざしき童子のはなし』のメッセージや考察
- 『宮沢賢治』について
『ざしき童子のはなし』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
宮沢賢治の「ざしき童子のはなし」は、日本の民間伝承に登録する「ざしき童子(ざしきぼっこ)」という不思議な存在についての短編小説です。
作品は三つの異なるエピソードから構成されています。
第一のエピソードでは、昼間、大人たちが山に働きに出かけている間、二人の子どもが庭で遊んでいました。
誰もいないはずの家の中から、突然「ざわっざわっ」という箒の音が聞こえてきます。
子どもたちは恐る恐る座敷を覗いてみますが、そこには誰もおらず、ただ日の光が部屋に降り注いでいるだけでした。
これがざしき童子の存在を感じさせる不思議な現象として描かれています。
第二のエピソードでは、祝いの席に招かれた十人の子どもたちが、手をつないで「大道めぐり、大道めぐり」と唱えながら座敷の中をぐるぐると回って遊んでいました。
しかし、いつの間にか子どもの数が十一人に増えていることに気づきます。
大人がそのうちの一人が「ざしきぼっこ」だと言いますが、どの子も自分はざしきぼっこではないと主張します。
第三のエピソードでは、はしかで寝込んでいた子どものために延期された如来様のお祭りの話が描かれています。
他の子どもたちはその子に対して不満を抱き、遊ばないと約束していました。
しかし、その子が来たと思って隠れた先の座敷に、その子がすでに座っていたのです。
みんなは「ざしきぼっこだ」と叫んで逃げ出し、残されたざしきぼっこは泣きました。
最後に、北上川の朗妙寺の渡し守が語る話として、旧暦八月十七日の夜に、紋付きを着て刀を差し、袴をはいた子どもを対岸に渡したエピソードが紹介されます。
その子は「笹田の家に長くいたけれどもう飽きたから、更木の斎藤の家に行く」と告げました。
その後、笹田の家は没落し、更木の斎藤の家は繁栄したといいます。
これらのエピソードを通して、宮沢賢治は日本の民間信仰に登場する「ざしき童子」という不思議な存在を、幻想的かつ身近な存在として描き出しています。
主な登場人物
- ざしき童子(ざしきぼっこ)
家に住み着く精霊的な存在。箒の音を立てたり、子どもの集まりに紛れ込んだり、姿を変えて現れたりする。その家に留まれば繁栄をもたらし、去れば衰退の原因となるとされる。 - 二人の子ども(第一のエピソード)
昼間、庭で遊んでいた子どもたち。家の中から聞こえる不思議な箒の音を探しに行く。 - 十人(十一人)の子どもたち(第二のエピソード)
お振舞いに呼ばれて座敷で遊んでいた子どもたち。いつの間にか一人増えていることに気付く。 - はしかの子ども(第三のエピソード)
はしかにかかったために如来様のお祭りが延期された子ども。他の子どもたちから恨まれていた。 - 渡し守(第四のエピソード)
北上川の朗妙寺の渡し守。旧暦八月十七日の夜に不思議な子どもを船で渡した体験を語る。
『ざしき童子のはなし』の重要シーンまとめ

この章では「ざしき童子のはなし」のキーとなるシーンをまとめています。
誰もいないはずの家の中から「ざわっざわっ」という箒の音が聞こえてくる不思議な現象。二人の子どもが恐る恐る確かめに行くが、座敷には誰もおらず、ただ日の光が降り注いでいるだけだった。目に見えないざしき童子の存在を暗示する神秘的なシーン。
お振舞いに呼ばれた十人の子どもたちが「大道めぐり、大道めぐり」と唱えながら座敷の中をぐるぐる回って遊んでいると、いつの間にか十一人になっていた。しかし、どの子も自分はざしき童子ではないと主張する。実体を持ちながらも正体を明かさないざしき童子の特性を表現している。
はしかの子どものために延期された如来様のお祭りで、子どもたちがその子に腹を立て、来たと思って隠れた先の座敷に、その子がすでに座っていた。みんなが「ざしきぼっこだ」と叫んで逃げ出すと、残されたざしきぼっこは泣いた。人間の子どもたちに受け入れられない悲しみを表現している。
旧暦八月十七日の夜、渡し守が紋付きを着て刀を差し、袴をはいた上品な子どもを船で対岸に渡した。その子は「笹田の家に長くいたけれどもう飽きたから、更木の斎藤の家に行く」と告げた。後に笹田の家は没落し、斎藤の家は繁栄した。ざしき童子が家の繁栄と衰退に関わる存在であることを示している。
 あおなみ
あおなみざしき童子は日本の民間信仰に登場する不思議な存在ですが、宮沢賢治はそれを単なる迷信ではなく、子どもの姿をした神秘的な存在として描いています。
特に「泣くざしき童子」のシーンは、排除されることの悲しみという普遍的なテーマに昇華させていると感じます。
『ざしき童子のはなし』の考察や気づき


「宮沢賢治」が『ざしき童子のはなし』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 共存と排除
ざしき童子は家の中に住み着き、時に人間と交流しようとするが、正体を知られると排除される。人間社会における「異質なもの」との共存の難しさと、排除することの悲しみが描かれている。賢治は異質なものを受け入れる寛容さの大切さを伝えようとしたのではないだろうか。 - 子どもの感受性
物語の視点は常に子どもたちにある。大人には見えない、感じられないものを子どもたちは感じ取っている。賢治は子どもの持つ純粋な感受性や想像力を尊重し、それを通して私たちが失ってしまった何かを取り戻そうとしているのではないだろうか。 - 孤独と受容
泣くざしき童子のエピソードは特に印象的だ。他の子どもたちから排除され、孤独に涙するざしき童子の姿は、賢治自身の孤独感の投影かもしれない。賢治は互いに理解し合い、受け入れ合うことの大切さを訴えている。



宮沢賢治は民間伝承を題材にしながらも、そこに普遍的な人間の感情や社会の問題を織り込んでいます。ざしき童子という存在を通して、私たちに「目に見えないものへの敬意」と「異質なものへの寛容さ」を問いかけているように思えます。
宮沢賢治について
宮沢賢治(1896-1933)は、岩手県花巻出身の童話作家、詩人です。
「ざしき童子のはなし」に見られるように、賢治の作品には東北地方の民間伝承や風土が色濃く反映されています。
北上川の描写や座敷童子という東北地方の民間信仰を題材にした本作は、賢治の郷土への深い愛着と理解を示しています。
賢治は仏教、特に法華経の熱心な信者でもありました。
「ざしき童子のはなし」の中でも如来様のお祭りが登場し、旧暦八月十七日という日付が重要な意味を持つなど、仏教的要素が見られます。
また、目に見えない存在への畏敬の念や、すべての生き物との共生という考え方も、彼の仏教思想に根ざしています。
科学者としての側面も持っていた賢治は、合理的な思考と神秘的な感覚を両立させていました。
「ざしき童子のはなし」でも、不思議な現象を北上川の水音や百舌の声など科学的に説明できるものと比較しながらも、最終的には神秘的な存在として描いています。
また、賢治の作品に共通する「異質なものへの理解と共感」というテーマは、彼自身が社会の中で感じていた孤独や疎外感から生まれたものかもしれません。
ざしき童子が泣くシーンは、理解されない悲しみを表現していると同時に、賢治自身の内面を映し出しているようにも感じられます。
賢治は37歳という若さで亡くなりましたが、彼の残した作品は今なお多くの人々に読み継がれています。
「ざしき童子のはなし」のような民話的な短編から「銀河鉄道の夜」のような壮大な物語まで、様々な形で賢治は私たちに想像力の豊かさと共感の大切さを教えてくれています。
『ざしき童子のはなし』のあおなみのひとこと感想



「ざしき童子のはなし」は、目に見えない存在との共存という普遍的なテーマを、東北の民間伝承を通して幻想的に描いた作品です。
特に印象的なのは、排除されて泣くざしき童子の姿。
そこには異質なものを受け入れられない人間社会への問いかけがあります。
宮沢賢治特有の優しさと哀しみが交錯する世界観に、今なお心を揺さぶられます。
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!