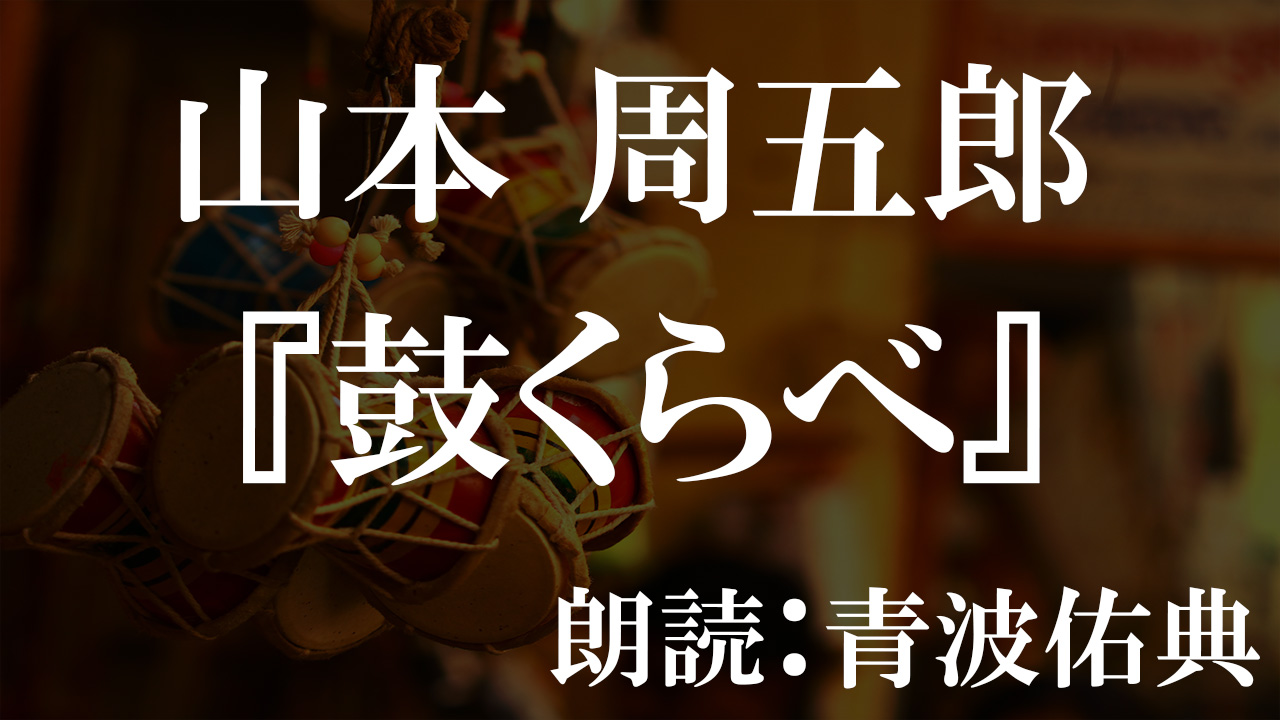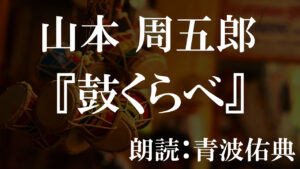競争社会を生きる現代人に贈る、心を揺さぶる珠玉の短編。勝つことだけを目指していた少女が、ある老人との出会いで「本当に大切なもの」に気づく物語です。
クライマックスで主人公が下した驚きの決断に、きっとあなたも涙するはず。
山本周五郎が描く、勝負を超えた芸術の本質とは?最後まで読めば、人生観が変わるかもしれません。
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『鼓くらべ』の物語概要とあらすじ
- 『鼓くらべ』のメッセージや考察
- 『山本周五郎』について
『鼓くらべ』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
加賀国森本の絹問屋の娘・お留伊は、15歳にして鼓の名手として知られていた。美しいが冷たく勝気な性格の彼女は、正月に金沢城で開催される鼓くらべに向けて日々練習に励んでいた。対戦相手は津幡の能登屋のお宇多という16歳の娘で、お留伊は相手の探りを警戒しながら、賞を得ることだけを目指していた。
ある日、籬の陰から痩せた老人が現れる。老人は旅の絵師と名乗り、お留伊の鼓の音に誘われて庭先まで来たという。最初は疑っていたお留伊だったが、次第に老人に心を開いていく。老人は貧しい旅暮らしの中で学んだ人生の教訓を語り、「人はもっと譲り合わなければならない、慈悲を持たなければならない」と優しく諭した。
老人は昔、観世市之亟という囃子方が「友割り鼓」という神技で勝負に勝った後、自ら鼓を持つ腕を折って姿を消した話をする。そして「芸術は人を楽しませ、心を清くするもので、人と優劣を争う道具ではない」とお留伊に語りかけた。
金沢での稽古を終え、自信満々で鼓くらべに臨んだお留伊。曲の途中、必死な表情で打つお宇多の顔を見た瞬間、老人の言葉が蘇る。老人こそが市之亟だと悟ったお留伊は、突然鼓を止めてしまう。師匠は取り乱したが、お留伊の心には新しい喜びが溢れていた。
森本に戻ったお留伊は、老人が亡くなったことを知る。遺体の前で彼女は初めて温かい涙を流し、「お教えで眼が明きました」と語りかける。そして生まれ変わった気持ちで、老人の枕辺で心を込めて鼓を打つのだった。
主な登場人物
- お留伊(おるい)
15歳の絹問屋の娘。鼓の名手だが、冷たく勝気で驕った性格。老絵師との出会いを通じて、芸術の本質と人間としての謙虚さを学び、精神的に成長する。 - 老絵師(観世市之亟と思われる)
痩せた旅の絵師。福井出身で病を抱えながら故郷へ帰る途中、森本に滞在。お留伊の鼓に魅せられ、優しく人生の真理を説く。左腕をふところに隠しており、かつての名囃子方・市之亟である可能性が示唆される。 - 観世仁右衛門
お留伊の師匠。彼女の才能を高く評価し、鼓くらべへの出場を勧める。本番でお留伊が途中で演奏を止めたことに激しく動揺する。 - お宇多
16歳の能登屋の娘。お留伊のライバルとして鼓くらべに出場。必死に勝とうとする執念の表情が、お留伊に老人の教えを思い出させるきっかけとなる。
『鼓くらべ』の重要シーンまとめ

この章では「鼓くらべ」のキーとなるシーンをまとめています。
籬の菊の陰から現れた痩せた老人。お留伊は最初、ライバルの能登屋から送られたスパイだと疑うが、老人は旅の絵師だと語る。左手をふところに隠した貧しい姿に、お留伊は卑しさを感じながらも、自分の鼓を褒める老人に次第に心を開いていく。
病床の老人がお留伊に語る、観世市之亟の伝説。御前で鼓くらべに勝ち、相手の鼓を気合で割った市之亟が、その後自ら鼓を持つ腕を折って姿を消したという話。老人は「芸術は人の心を楽しませ、清くするもので、人と優劣を争う道具にすべきではない」と説く。
金沢城での鼓くらべ。優位に進めていたお留伊は、血の気を失い必死な表情のお宇多を見て、老人の言葉を思い出す。老人が市之亟だと悟った瞬間、彼女は鼓を止める。勝利よりも大切なものに気づいた彼女の心には、新しい喜びが溢れた。
亡くなった老人の枕辺で、お留伊は生まれ変わった気持ちで鼓を打つ。「お教えで眼が明きました」と涙ながらに語りかけ、勝ち負けを超えた純粋な芸術として、心を込めて「男舞」を奏でる。
 あおなみ
あおなみ勝負を放棄した瞬間こそが、お留伊が真の芸術家として生まれ変わった瞬間でした。老人への感謝の演奏は、作品全体のクライマックスとして深い感動を呼び起こします。
『鼓くらべ』の考察や気づき


「山本周五郎」が『鼓くらべ』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 謙虚さと人間的成長
冷たく勝気だったお留伊が、老人との出会いを通じて謙虚さを学ぶ過程が丁寧に描かれています。「人はもっと譲り合わなくてはいけない」という老人の言葉は、単なる道徳的教訓ではなく、芸術家として、人間としての成熟に不可欠な要素として提示されています。真の強さとは、勝つことではなく、執着を手放せることだと作者は語っているのです。 - 師弟関係の真の意味
形式的な師匠である仁右衛門よりも、老絵師こそがお留伊の真の師匠でした。技術を教えるだけでなく、芸術の精神性や人生の真理を伝えることが、本当の師弟関係だと作者は示しています。最後にお留伊が老人を「お師匠さま」と呼ぶシーンは、この物語の核心を象徴しています。 - 自己犠牲と解放
市之亟が自ら腕を折ったこと、お留伊が勝利を捨てたことは、一見すると自己犠牲に見えますが、実は執着からの解放でした。勝負への執念を手放した瞬間、お留伊は「広い野原へ解放されたような軽い気持ち」を感じます。作者は、真の自由とは何かを失うことではなく、こだわりを捨てることで得られると伝えています。



山本周五郎は芸術論を超えて、人間としてどう生きるべきかという普遍的なテーマを、能楽という日本の伝統文化を通じて見事に描き出しています。
山本周五郎について
山本周五郎(1903-1967)は、昭和を代表する時代小説作家です。『鼓くらべ』に見られるような、勝負や名誉よりも人間の内面的成長を重視する姿勢は、彼の作品全体を貫くテーマです。
周五郎は直木賞の受賞を二度辞退したことで知られています。『鼓くらべ』でお留伊が賞を放棄したように、周五郎自身も文学賞という「勝負」よりも、作品そのものの価値を重んじる姿勢を貫きました。この作品は、作者自身の芸術観や人生観を色濃く反映していると言えるでしょう。
彼の作品には、社会の底辺で生きる人々や、挫折を経験した人物が多く登場します。『鼓くらべ』の老絵師も、栄光の過去を捨て、貧しい旅暮らしの中で人生の真理に到達した人物として描かれています。周五郎は常に、外面的な成功よりも内面的な充実を、競争よりも共生を説き続けた作家でした。
『鼓くらべ』のあおなみのひとこと感想



勝つことだけを目指していたお留伊が、老人との出会いで真の芸術の美しさに目覚める物語に深く感動しました。現代社会でも競争が重視されがちですが、本当に大切なものは何かを問いかけてくる作品です。最後の枕辺での演奏シーンは、涙なしには読めません。
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!