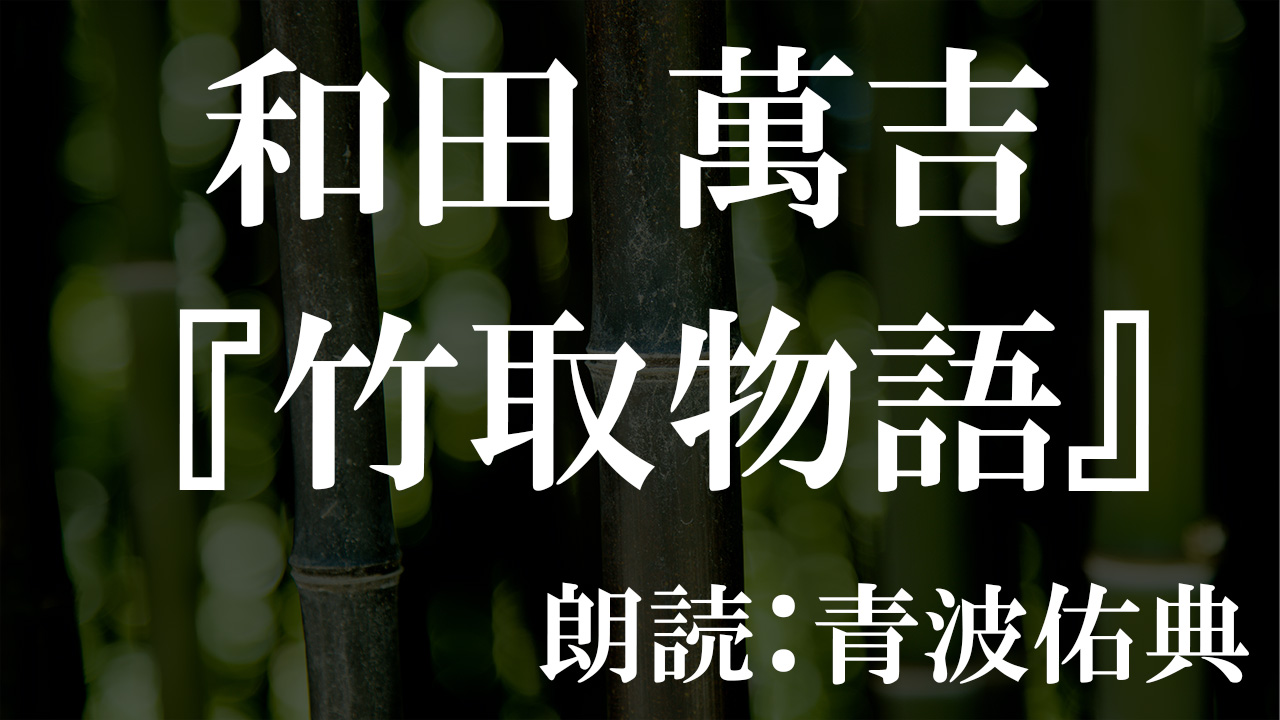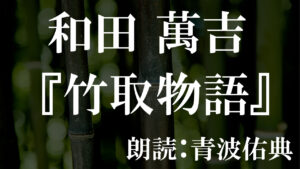月から舞い降りた美しき姫と、彼女を愛した人々の物語。
千年の時を超えて今なお心を揺さぶる『竹取物語』は、なぜこれほどまでに私たちを魅了するのでしょうか。
光る竹の発見から月への帰還まで、権力も富も通用しない姫の前で、人間たちはただ無力でした。
この記事では日本最古の物語が秘める、切なくも美しいメッセージを紐解いていきます。
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『竹取物語』の物語概要とあらすじ
- 『竹取物語』のメッセージや考察
- 『和田萬吉』について
『竹取物語』のあらすじと登場人物について
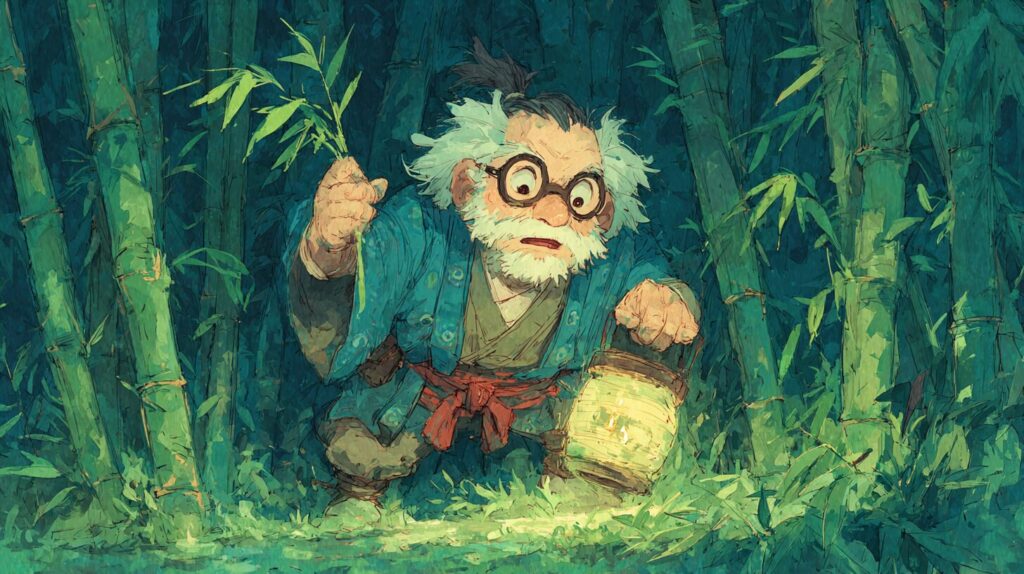
あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
竹取の翁と呼ばれる讃岐の造麻呂は、ある日光る竹の中から三寸ほどの美しい女の子を発見します。天からの授かりものと考えた翁は、妻とともにこの子を大切に育てました。不思議なことに、その後翁が竹を切ると節の間に黄金が入っているようになり、家は次第に裕福になっていきます。
女の子は驚異的な速さで成長し、わずか三ヶ月で立派な少女となりました。嫋竹の赫映姫(なよたけのかぐやひめ)と名付けられた彼女は、この世のものとは思えない美しさで、家中を光り輝かせるほどでした。
姫の噂を聞いた五人の高貴な求婚者たちが現れますが、姫は彼らにそれぞれ難題を課します。石造皇子には仏の御石の鉢、車持皇子には蓬莱山の玉の枝、阿倍右大臣には火鼠の皮衣、大伴大納言には龍の首の玉、石上中納言には燕の子安貝を求めました。五人はそれぞれ工夫を凝らしますが、偽物を持ってきたり、命を落としかけたりと、すべて失敗に終わります。
帝も姫の美しさの噂を聞き、宮仕えを命じますが、姫は頑なに拒みます。帝が自ら訪れても、姫は影のように消えてしまい、連れて行くことはできませんでした。
やがて春が来ると、姫は月を見ては悲しむようになります。実は姫は月の都の住人で、八月十五夜に迎えが来ることを明かすのです。翁は帝に助けを求め、二千人の武士が家を守りますが、月からの使者が現れると、誰もが力を失ってしまいます。姫は翁夫婦と帝に別れの手紙と不死の薬を残し、天の羽衣を着て月へと帰っていきました。悲しみに暮れる翁夫婦を残して。
帝は不死の薬を駿河の国の天に最も近い山で焚かせ、その煙は今も立ち昇っているといいます。この山が富士山と呼ばれるようになった由来とされています。
主な登場人物
- 竹取の翁(讃岐の造麻呂)
竹を取って生計を立てる老人。光る竹の中からかぐや姫を見つけ、実の娘のように大切に育てる。姫が月に帰る時には激しく悲しみ、引き留めようとする心優しい養父。 - 嫋竹の赫映姫(かぐやひめ)
竹の中から生まれた、この世のものとは思えない美しさを持つ少女。月の都の住人で、地上での罪を償うために一時的に地上に降ろされていた。知的で意志が強く、五人の求婚者たちに難題を課す。 - 石造皇子
五人の求婚者の一人。ずる賢く、天竺に行ったふりをして山寺の石の鉢を持ってくるが、光らないため見破られる。 - 車持皇子
巧みな策略家。職人に玉の枝を作らせて本物と偽るが、職人が報酬を求めて現れたことで嘘が発覚する。 - 阿倍右大臣
財産家。唐船に火鼠の皮衣を注文するが、火をつけると燃えてしまい失敗する。 - 大伴大納言
家来に龍の首の玉を取りに行かせるが、家来たちは従わず。自ら海に出て嵐に遭い、死にかける。 - 石上中納言
燕の子安貝を取ろうとして高所から落下し、腰を痛め病気も加わって死亡。五人の中で最も悲惨な結末を迎える。 - 帝(みかど)
時の天皇。姫の美しさに心を奪われ、宮仕えを命じるが拒まれる。姫が影のように消える不思議を体験する。姫が月に帰った後も、その思い出を胸に不死の薬を焚く。 - 翁の妻(お婆さん)
姫を籠の中で大切に育てる優しい養母。姫との別れを深く悲しむ。
『竹取物語』の重要シーンまとめ

この章では「竹取物語」のキーとなるシーンをまとめています。
竹取の翁が光る竹を見つけ、その中に三寸ほどの美しい女の子を発見する場面。この奇跡的な出会いが物語のすべての始まり。翁が「天が我が子として与えてくれたもの」と考え、手のひらに載せて持ち帰る描写は、親子の絆の原点を示している。
石造皇子の偽物の鉢、車持皇子の職人による偽造、阿倍右大臣の燃える皮衣、大伴大納言の嵐での遭難、石上中納言の転落事故。それぞれの求婚者が知恵を絞りながらも、欲望に駆られて失敗していく様子は、人間の弱さと滑稽さを浮き彫りにする。特に石上中納言が古糞をつかんで喜ぶ場面は悲喜劇的。
帝が姫を連れて行こうとすると、姫の体が影のように消えてしまう神秘的な場面。権力を持つ帝でさえも姫を自分のものにできないという、物語の核心的なメッセージが込められている。姫の超自然的な存在が明確に示される重要なシーン。
春先から姫が月を見ては悲しむようになり、七月十五夜には泣いてばかりいる場面。「月の都の者で、八月十五夜に帰らなければならない」という告白は、物語最大の転換点。翁夫婦の「気違いのように泣き出す」描写が、別れの悲しみを強烈に印象づける。
満月の十倍の光とともに月からの使者が現れ、二千人の武士も力を失う圧倒的な場面。堅く閉ざした土蔵の戸が自然と開き、姫の体がするすると出ていく描写は幻想的。天の羽衣を着た姫が百人の天人に囲まれて空高く昇っていく情景は、美しくも切ない。翁夫婦が声をあげて泣く姿に、地上での愛情の深さが表現されている。
帝が駿河の国の天に最も近い山で不死の薬を焚かせる結末。「姫のいない世界で永遠に生きても意味がない」という帝の想いが込められた行為。薬の煙が今も立ち昇るという結びは、姫への思慕が永遠に続くことを象徴している。
 あおなみ
あおなみ竹取物語の重要シーンは、奇跡的な出会いから始まり、人間の欲望と権力の限界を経て、避けられない別れへと向かう構成が見事です。地上と天上、人間と超越的存在、一時的な幸福と永遠の別離という対比が、各シーンを通じて美しく描かれています。
『竹取物語』の考察や気づき


「和田萬吉」が『竹取物語』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 手に入らないものへの憧憬
竹取物語は、どれだけ富や権力を持っていても、本当に大切なものは手に入らないという真理を描いています。五人の貴族たちは地位も財産もありながら姫を得られず、帝という最高権力者でさえも姫を自分のものにできませんでした。人間の欲望の限界と、それを超越した存在の美しさを対比させることで、この世ならぬものへの憧れと諦念を表現しているのです。 - 人間の欲望と虚栄の批判
五人の求婚者たちの失敗は、人間の欲望がいかに愚かで滑稽なものかを示しています。偽物を本物と偽る者、無謀な冒険に出て命を危険にさらす者。特に石上中納言が燕の古糞をつかんで喜ぶ場面は、欲に目が眩んだ人間の滑稽さを痛烈に風刺しています。作者は貴族社会の虚飾を批判的に描いているのです。 - 日本的美意識の表現
かぐや姫という存在そのものが、日本人が理想とする美の象徴です。「この世界にないくらい」の美しさ、近づけば消えてしまう儚さ、月という清浄なイメージ。これらは日本文化特有の「もののあわれ」や「幽玄」といった美意識を体現しています。手に入らないからこそ美しい、失われるからこそ尊いという価値観が、物語全体に流れているのです。



竹取物語は表面的には不思議な姫の物語ですが、その奥には人間存在の根源的なテーマが隠されています。愛と別れ、欲望と挫折、現世と来世、そして何より「美しいものは永遠ではない」という真理。作者は平安時代の貴族社会を舞台にしながら、時代を超えて共感できる普遍的なメッセージを込めたのでしょう。
和田萬吉について
竹取物語は「和田萬吉」の名で伝えられていますが、実は原作者は不詳です。平安時代初期(9世紀後半から10世紀初頭)に成立したとされる日本最古の物語文学で、「物語の出で来はじめの祖(おや)」と源氏物語の中でも評されています。
この物語が生まれた平安時代は、貴族文化が爛熟し、仮名文字が発達した時期でした。作者は貴族社会の内情をよく知る教養人だったと推測され、五人の求婚者たちの描写には当時の貴族たちへの風刺が込められています。石造皇子のずる賢さや、大伴大納言の無謀さなど、実在の貴族たちをモデルにしたのではないかとも言われています。
竹取物語には中国の伝説や仏教思想の影響も見られますが、月を舞台にした幻想性や、かぐや姫という存在の描き方には、日本独自の美意識が色濃く反映されています。作者は外来文化を巧みに取り入れながら、純粋に日本的な感性で物語を紡いだのです。
また、この物語は富士山の由来譚としても機能しており、不死の薬を焚いた山が「不死の山(富士山)」となったという結末は、民間伝承と文学を結びつける試みでもありました。作者は単なる娯楽作品ではなく、日本の風土と結びついた神話的物語を創造しようとしたのかもしれません。
『竹取物語』のあおなみのひとこと感想



千年以上前の物語なのに、今読んでも色褪せない魅力があります。かぐや姫の儚い美しさ、翁夫婦の深い愛情、そして避けられない別れの悲しさ。特に月からの迎えの場面は幻想的で圧倒されました。手に入らないものほど美しいという真理を、こんなにも優雅に描いた物語は他にないでしょう。日本文学の原点がここにあると実感します。
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!