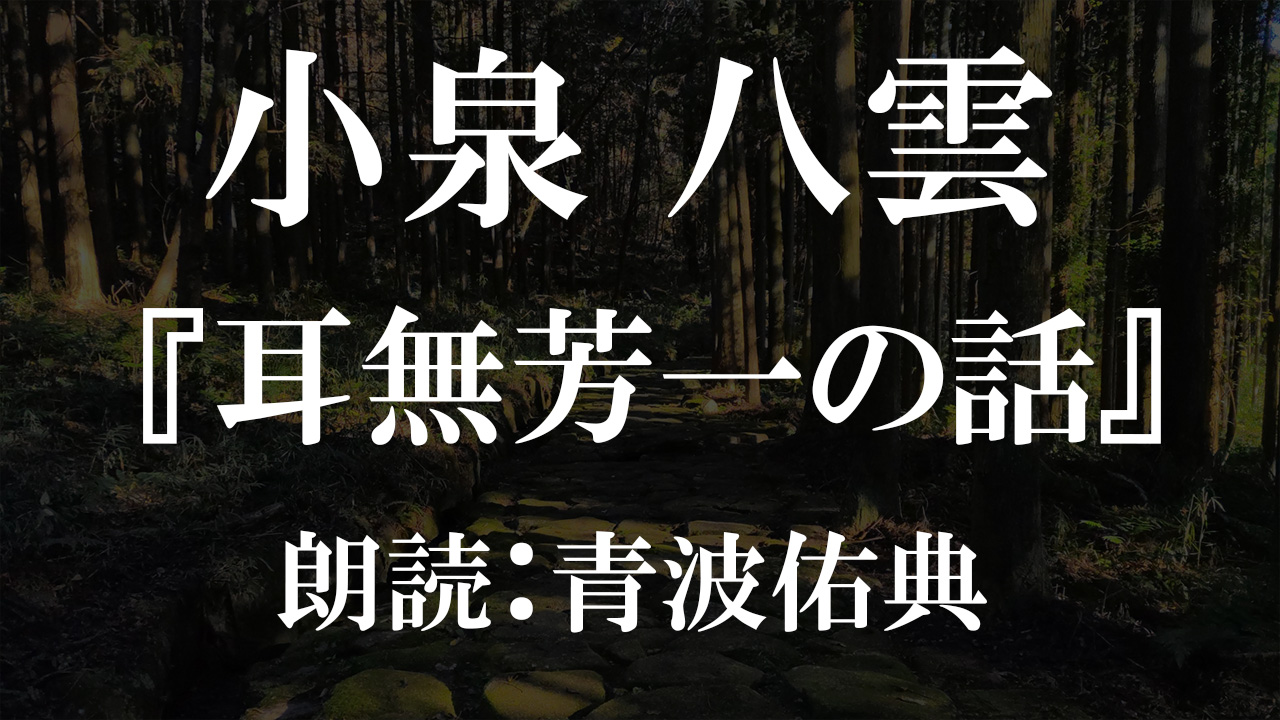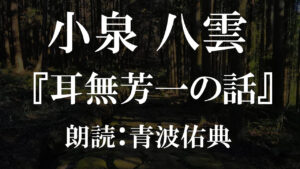舞台は怨念渦巻く壇ノ浦。
その地で、魂を揺さぶる琵琶の音色を奏でる盲目の芳一。
彼の才能は、生者の心を捉えるだけでなく、恐ろしい亡霊までも引き寄せてしまう…。
毎夜繰り返される禁断の演奏。芳一の身に迫る想像を絶する危機とは?
そして、彼を救おうとする心優しき住職の奮闘は?
ページをめくる手が止まらない、美しくも妖しい小泉八雲の傑作怪談「耳無芳一の話」の世界へ、あなたも足を踏み入れてみませんか?
その結末に、きっとあなたは言葉を失うでしょう。
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『耳無芳一の話』の物語概要とあらすじ
- 『耳無芳一の話』のメッセージや考察
- 『小泉八雲』について
『耳無芳一の話』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
舞台は七百年以上前の下ノ関海峡、壇ノ浦。
源氏と平家の最後の戦いが行われたこの地は、平家一門の怨霊が彷徨うと語り継がれていました。特に、入水した幼い安徳天皇や多くの貴族たちの霊は、夜な夜な海面に鬼火を灯し、風の強い夜には戦の叫び声のようなものが聞こえると恐れられていました。
そんな中、赤間ヶ関(現在の山口県下関市)に盲目の琵琶法師、芳一が住んでいました。
幼い頃から琵琶の弾奏と語りに秀でていた芳一は、特に平家物語、中でも壇ノ浦の合戦の場面を語らせると、鬼神さえも涙を流すほどの才能を持っていました。
貧しいながらも生計を立てていた芳一には、心優しい理解者がいました。
それは阿彌陀寺の住職で、詩歌や音楽を愛するこの住職は、しばしば芳一を寺に招いて演奏させていました。
やがて住職はその才能に深く感銘を受け、芳一に寺を住まいとして提供します。
芳一は感謝してそれを受け入れ、普段は住職のために琵琶を奏でることで恩返しをしていました。
ある夏の夜、住職は檀家の法事に出かけ、芳一は一人寺に残されました。
暑い夜、芳一は涼むために寝室の前の縁側に出て、琵琶を爪弾きながら住職の帰りを待っていました。
夜半を過ぎても住職は戻らず、外で過ごしていた芳一の耳に、裏門から近づく足音が聞こえました。
庭を横切り、縁側のすぐそばに立ち止まったのは、住職ではありませんでした。
突然、低いけれど力強い声が芳一の名を呼びました。
驚いた芳一が返事をためらっていると、その声は再び、今度は厳しい命令のように芳一を呼びつけました。
「はい!」と恐る恐る返事をした芳一に、見知らぬ男は自分が近くに住む者の使いであり、高貴な身分の殿様が壇ノ浦を見物された際、芳一の語りを聞きたいと仰せつかっていると告げました。
そして、すぐに琵琶を持って殿の待つ屋敷へ来るようにと促しました。
当時の武士の命令に逆らうことは難しく、芳一は男に連れられて夜の闇の中へ出かけました。
案内する男は足早で、その手は鉄のように強く感じられました。
やがて立派な門構えの屋敷に到着し、多くの女官たちが仕える広大な屋敷の中へ案内されました。
そして、大勢の人が集まる広間へ通され、そこで芳一は琵琶を奏で、平家物語を語るように命じられました。
特に、聴衆の求めに応じ、壇ノ浦の合戦、そして幼い天皇や女たちの悲劇的な最期を語ると、その悲痛な語りに人々は深く心を打たれ、激しく泣き崩れるほどでした。
演奏後、芳一はその才能を大いに褒められ、殿様から今後六日間、毎晩同じ時間に演奏するようにと命じられました。
ただし、この訪問について誰にも話してはならないと強く戒められました。
言われた通り、翌晩も芳一は迎えに来た侍に連れられ、同じ屋敷で演奏しました。
しかし、二度目の訪問の際、寺の下男が芳一が夜中に外出していることに気づき、住職に報告しました。
住職は芳一を呼びつけ、心配していたことを優しく諭しましたが、芳一は曖昧な返事をするばかりでした。
不審に思った住職は、下男に芳一の後をつけるように命じました。
その晩、下男たちは芳一が寺を出て行くのを見つけ、提灯を灯して後を追いました。
雨の降る暗い夜道で芳一は驚くほど早く歩き、下男たちはすぐに彼を見失ってしまいました。
やがて浜辺の方から寺に戻る途中、下男たちは阿彌陀寺の墓地から激しい琵琶の音が聞こえてくるのに気づきました。
恐る恐る近づくと、雨の中、安徳天皇の墓の前で芳一が一人琵琶を奏で、壇ノ浦の合戦を語っていたのです。
その周囲には、無数の鬼火が揺らめいていました。
下男たちは芳一に声をかけましたが、彼は全く気づきません。
必死に呼びかけ、無理やり彼を捕まえて寺へ連れ帰りました。
住職は芳一の身に起こったことを詳しく聞き、それが平家の亡霊たちによるものだと悟りました。
亡霊は芳一の語りを気に入り、毎晩彼を呼び出していたのです。
このままでは芳一は命を落としかねないと考えた住職は、芳一の全身に魔除けのためのお経、般若心経を書きつけることにしました。
日没前、住職と納所は芳一の全身、足の裏に至るまで丁寧に経文を書き記しました。
そして住職は芳一に、今夜迎えが来ても決して返事をしたり動いたりせず、静かに座っているようにと厳しく言い聞かせました。
夜になり、住職と納所が出かけた後、芳一は言われた通り縁側に座って待ちました。
やがて、あの低い声が再び芳一の名を呼びました。
しかし芳一は息を潜め、動かずにいました。何度か声が繰り返されましたが、芳一は決して応じませんでした。
すると、足音が縁側に上がり、芳一のすぐそばに近づきました。
しばらくの静寂の後、荒々しい声が言いました。「ここに琵琶があるが、琵琶法師は…耳が二つあるばかりだ!」そして、芳一は両耳を掴まれ、引きちぎられる激痛を感じました。それでも彼は決して声を出さず、じっと耐え忍びました。
翌朝、帰ってきた住職は、血まみれの縁側と、両耳から血を流しながらも座禅の姿勢でいる芳一を発見しました。
住職は、経文を書き忘れた耳のせいでこのような事態になったことを深く悔い、芳一を介抱しました。
この出来事以来、芳一は「耳無芳一」と呼ばれるようになりましたが、彼の才能は広く知れ渡り、多くの人々が彼の語りを求めて赤間ヶ関を訪れるようになったということです。
主な登場人物
- 芳一
盲目の琵琶法師で、平家の物語の弾き語りに優れている。平家の亡霊に招かれ、毎晩墓地で演奏する羽目になる。 - 住職
芳一が身を寄せる阿彌陀寺の住職。芳一の才能を認め、親身に世話をする。亡霊から芳一を守ろうと奔走する。 - 侍
芳一を高貴な人物の屋敷へと案内する謎の侍。実は平家の亡霊の使いである。 - 老女
高貴な屋敷に仕える女房の頭と思われる女性。芳一に平家の物語の演奏を依頼する。平家の亡霊の一人である可能性が高い。 - 平家の亡霊
壇ノ浦の合戦で滅亡した平家一門の怨霊。生前の栄華を偲び、芳一に物語の演奏を求める。 - 安徳天皇
壇ノ浦の合戦で入水した幼い天皇。彼の墓前で芳一は演奏していた。
『耳無芳一の話』の重要シーンまとめ

この章では「耳無芳一の話」のキーとなるシーンをまとめています。
盲目の芳一が、身分の高い人物に琵琶の演奏を頼まれたと告げられ、夜の屋敷へと連れて行かれる場面。物語の始まりであり、異質な世界への導入となる。
芳一が平家の亡霊たちの前で、壇ノ浦の合戦の様子を渾身の力で演奏する場面。芳一の卓越した才能と、亡霊たちの悲痛な感情が伝わる。
芳一が毎晩寺を抜け出していることが発覚し、住職が異変を察知する場面。物語の不気味さが増し、芳一の身に危険が迫っていることが示唆される。
雨の夜、下男たちが墓地で無数の鬼火の中で琵琶を弾く芳一を目撃する場面。幻想的で衝撃的な光景であり、芳一が亡霊に取り憑かれていることが明らかになる。
亡霊から芳一を守るため、住職が彼の全身に経文を書きつける場面。住職の強い決意と、事態の深刻さが伝わる重要な場面。
芳一が住職の言いつけを守り動かない中、亡霊が琵琶を持つ芳一の耳だけを「琵琶法師」と認識して切り取る場面。最も恐ろしく、悲劇的なクライマックス。
芳一が耳を失いながらも生き残り、「耳無芳一」としてその名を知られるようになる場面。悲劇的な結末でありながら、芳一の才能が世に認められるという皮肉な結末でもある。
『耳無芳一の話』の考察や気づき

「小泉八雲」が『耳無芳一の話』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 芸術の持つ力と危険性
芳一の卓越した琵琶の才能は、人々の心を捉える一方で、異界の存在をも引き寄せてしまう。芸術が持つ強烈な力は、時に予期せぬ危険を招く可能性を暗示している。才能は諸刃の剣となりうるという警鐘とも取れる。 - 信仰と救済の力
住職が経文を芳一の全身に書きつける行為は、信仰の力によって災厄から身を守ることができるという信念を示している。仏教的な救済の思想を通して、精神的な支えの重要性を伝えている。 - 人間の無力さと運命の残酷さ
盲目の芳一は、自身の才能ゆえに亡霊に翻弄され、悲劇的な結末を迎える。人間の力では抗えない運命の残酷さや、個人の努力だけではどうにもならない力の前での無力さを感じさせる。
 あおなみ
あおなみ作者は、歴史の教訓、芸術の力、不可思議な存在への畏敬、信仰の意義、そして人間の宿命といった、多岐にわたるテーマをこの物語に織り込んでいると考えられそうですね。
小泉八雲について
「耳無芳一の話」の作者、小泉八雲(こいずみやくも、Lafcadio Hearn、ラフカディオ・ハーン、1850年6月27日 – 1904年9月26日)は、ギリシャ生まれのアイルランド系イギリス人の父とギリシャ人の母を持つ、複雑な出自の作家・ジャーナリストです。
彼は、日本文化に深く魅せられ、1890年に来日、後に日本に帰化して小泉セツと結婚し、小泉八雲と名乗りました。
「耳無芳一の話」は、八雲が日本各地の伝説や怪談を収集し、西洋の読者に向けて再話した作品群『怪談』(Kwaidan)の中に収録されています。
この作品を通して、八雲の日本文化、特にその神秘的な側面への深い関心と、それを魅力的に描写する才能を垣間見ることができます。
八雲と「耳無芳一の話」との関わりから見えてくる特徴:
- 日本の怪談・伝説への強い興味と探求心: 八雲は、日本各地に伝わる民話や伝説、特に怪談に強い興味を持ち、積極的に収集・研究しました。「耳無芳一の話」も、下関に伝わる平家と琵琶法師の伝説を基にしています。彼は、単に奇妙な話として紹介するのではなく、その背景にある歴史や文化、人々の信仰心などを深く理解しようと努めました。
- 異文化理解と紹介の視点: 西洋で生まれ育った八雲は、日本の文化や風習を西洋の読者に向けて分かりやすく、かつ魅力的に伝えるという意識を強く持っていました。「耳無芳一の話」においても、平家一門の悲劇や琵琶法師の役割、怨霊の概念など、日本の独特な要素を丁寧に描写し、異文化への理解を促そうとしています。
- 幻想的で詩的な文体: 八雲の文章は、幻想的で美しく、時に詩的な表現が特徴です。「耳無芳一の話」でも、夜の墓地の情景や琵琶の音色、亡霊の気配などが、繊細な言葉で描き出されています。これにより、読者は物語の世界に引き込まれ、怪談の持つ独特の雰囲気を深く味わうことができます。
- 人間の感情や心理への深い洞察: 単なる怪談としてだけでなく、登場人物の感情や心理描写も ശ്രദ്ധ深く行われています。芳一の恐怖や悲しみ、住職の慈悲心、亡霊たちの執念などが、読者の心に強く訴えかけます。八雲は、怪異な現象を通して、人間の普遍的な感情を描き出そうとしていたと言えるでしょう。
- 日本の伝統文化への敬意と愛情: 八雲の作品全体を通して、日本の伝統文化や人々の精神性に対する深い敬意と愛情が感じられます。「耳無芳一の話」においても、琵琶という伝統楽器や、鎮魂の儀式、信仰心などが重要な要素として描かれており、日本の文化に対する彼の温かい眼差しが伝わってきます。
「耳無芳一の話」は、小泉八雲が日本の怪談という素材を通して、日本の文化や人々の心を西洋に紹介しようとした代表的な作品の一つと言えるでしょう。
彼の異文化への深い理解と、それを魅力的に語る筆力によって、この物語は時代を超えて多くの人々に読み継がれています。
『耳無芳一の話』のあおなみのひとこと感想



平家一門の悲劇と怨念が、盲目の琵琶法師芳一の才能を通して鮮やかに描き出され、ぞっとするような恐怖と深い哀愁が心に残りました。
音楽の力、歴史の重み、そして見えないものの存在への畏怖を感じさせる、幻想的で印象的な物語でした。
耳を失ってもなお語り継がれる芳一の運命に、複雑な感情を抱きました。
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!