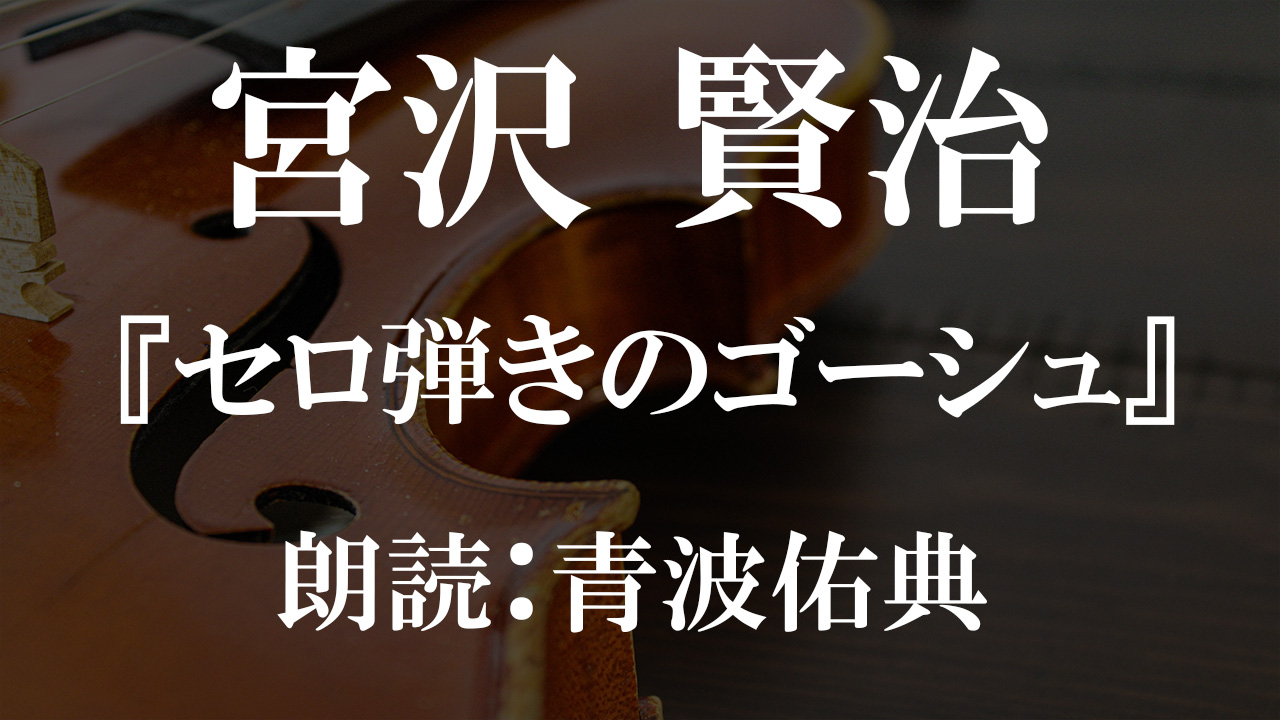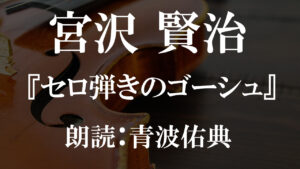「セロ弾きのゴーシュ」は、努力と成長を描いた宮沢賢治の名作。
音楽団で最も下手なゴーシュが、動物たちとの不思議な交流を通じて、音楽の本質を学び、ついには観客を魅了する演奏を披露するまでの物語です。
なぜゴーシュは成長できたのか?
動物たちは彼に何を教えたのか?
この記事では、あらすじや重要シーン、作品のメッセージをわかりやすく解説します。
最後まで読めば、あなたもゴーシュの物語に心を動かされること間違いなしです!
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『セロ弾きのゴーシュ』の物語概要とあらすじ
- 『セロ弾きのゴーシュ』のメッセージや考察
- 『宮沢賢治』について
『セロ弾きのゴーシュ』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
ゴーシュは町の活動写真館でチェロ(セロ)を弾く楽士だが、楽団の中で最も下手だとされ、楽長からいつも厳しく叱責されていた。
ある日、町の音楽会に向けた練習で、またも楽長に遅れや音程のズレを指摘され、悔しさに涙を流しながらも、一人で猛練習を続ける。
そんな彼のもとへ、ある夜、三毛猫が訪れ、シューマンの「トロメライ」を弾くよう求める。
しかし、ゴーシュは代わりに「インドの虎狩り」という激しい曲を弾き、猫は驚いて逃げてしまう。
次の晩にはカッコウがやってきて、正確なドレミファを教えてほしいと頼む。
ゴーシュは半ば呆れながらも演奏し、カッコウは夢中になって歌うが、彼自身もカッコウの歌のリズムや正確さに感心する。
さらに翌晩には、狸の子が訪れ、「愉快な馬車屋」をセロに合わせて演奏させてほしいと申し出る。
狸のリズム感に導かれながらゴーシュは演奏を続け、自らの技術の未熟さを改めて感じる。
ある夜、野ねずみの親子が訪れ、病気の子どもをゴーシュのセロの音で癒してほしいと頼む。
ゴーシュは半信半疑ながらもセロの中に子ねずみを入れ、ラプソディを演奏すると、子ねずみは元気を取り戻す。
こうした奇妙な夜を過ごしながら、ゴーシュの演奏は確実に上達していく。
そして音楽会当日、楽団の演奏は成功し、観客は熱狂的な拍手を送る。
さらにアンコールの要請に応え、ゴーシュが独奏を披露すると、聴衆はその迫力に圧倒される。
楽団の仲間たちも彼の成長を称賛し、楽長もその変化を認めるのだった。
夜、ゴーシュは自宅の窓を開け、遠くの空に向かって、かつて怒鳴りつけたカッコウに「すまなかった」と語りかけるのだった。
主な登場人物
- ゴーシュ
本作の主人公。町の活動写真館の楽団でチェロ(セロ)を弾く楽士。演奏が下手で楽長から厳しく叱責されるが、毎晩ひとりで練習を続ける。
動物たちとの交流を通じて成長し、最終的には見事な演奏を披露できるようになる。 - 楽長
ゴーシュが所属する楽団の指揮者。
ゴーシュの演奏技術が未熟なため、厳しく叱るが、それは楽団全体のレベルを向上させるためでもある。
音楽会の本番ではゴーシュの成長を認め、彼を称賛する。 - 三毛猫
ゴーシュのもとを最初に訪れた動物。半分熟したトマトを持ってきたが、ゴーシュに追い払われる。
それでも「シューマンのトロメライを弾いてほしい」と頼むが、ゴーシュは「インドの虎狩り」を激しく弾き、猫を驚かせる。
この出来事がゴーシュの音楽に対する新たな気づきを生むきっかけとなる。 - カッコウ
次にゴーシュを訪れた鳥。正確な「ドレミファ」を習いたいと願い、ゴーシュに指導を求める。
ゴーシュは半ば呆れながらも演奏し、カッコウは真剣に歌う。
最初はゴーシュが馬鹿にしていたが、次第にカッコウのリズムの正確さに感心するようになる。 - 狸の子
小太鼓の練習のため、ゴーシュのもとへやってきた狸の子ども。
「愉快な馬車屋」をセロに合わせて演奏し、ゴーシュのリズムのズレを指摘する。
ゴーシュは自分の演奏の問題点を自覚するようになり、演奏技術向上のきっかけを得る。 - 野ねずみの親子
病気の子ねずみを助けるため、ゴーシュのもとを訪れる。
ゴーシュのセロの音が治療のような効果を持つと信じており、ゴーシュは半信半疑ながらも演奏を続ける。
結果的に子ねずみは元気になり、ゴーシュは自分の演奏が人や生き物に影響を与える力を持っていることを実感する。
『セロ弾きのゴーシュ』の重要シーンまとめ

この章では「セロ弾きのゴーシュ」のキーとなるシーンをまとめています。
ゴーシュは楽団の中で最も演奏が下手で、楽長から厳しく叱責されます。
特に「表情がない」「感情が伝わらない」と指摘され、仲間たちも気の毒そうにするほどの実力不足。
このシーンが物語の導入となり、ゴーシュの努力と成長を強調する背景となります。
楽団での練習後、ゴーシュは自宅でセロを猛練習します。
一心不乱に弾き続け、気づけば夜中を過ぎ、疲れ果てるまで演奏を続ける。
このシーンは、彼の努力と執念を象徴しており、後の成長への伏線となります。
ゴーシュのもとを最初に訪れたのは三毛猫。「シューマンのトロメライを弾いてほしい」と頼みますが、ゴーシュは代わりに「インドの虎狩り」を激しく演奏し、猫を驚かせます。
このシーンでは、ゴーシュの感情的な演奏が描かれ、音楽の持つ「表現力」について考えさせられる場面です。
次に訪れたカッコウは「正確なドレミファを習いたい」と言います。
最初は馬鹿にしていたゴーシュですが、カッコウのリズムの正確さに次第に気づきます。
このシーンは、音楽の「リズム」と「正確さ」の重要性を示し、ゴーシュの演奏に影響を与えます。
狸の子が「小太鼓のリズムに合わせてほしい」と言い、セロと小太鼓のセッションを行います。
狸は「2番目の糸が遅れる」と指摘し、ゴーシュは自分のリズムのズレを自覚する。
このシーンを通じて、音楽における「リズムの精度」がゴーシュにとっての課題であることが明確になります。
野ねずみの親子が「病気の子どもをセロの音で治してほしい」と訪れます。
ゴーシュは最初は怒りますが、演奏すると本当に子ねずみが元気になる。
このシーンは、「音楽が人を癒す力を持つ」というテーマを象徴する場面であり、ゴーシュ自身も音楽の力を実感する転機となります。
ゴーシュたちの楽団は町の音楽会で「第六交響曲」を演奏し、大成功を収めます。
観客は大歓声と拍手を送り、楽長もゴーシュの成長を認めます。
これは、ゴーシュの努力が実った瞬間であり、物語のクライマックスとなる重要な場面です。
アンコールの要請があり、楽長はゴーシュにソロ演奏を任せます。
ゴーシュは「インドの虎狩り」をまるで怒れる象のように迫力満点で弾き、観客は圧倒される。
今までとは違う堂々とした演奏を披露し、成長が決定的になるシーン。
演奏会を終えたゴーシュは自宅の窓を開け、夜空を見ながらカッコウに向かって語りかける。
「すまなかったな。おれは怒ったんじゃなかったんだ。」
これは、ゴーシュが動物たちとの交流を通じて成長し、音楽への理解を深めたことを象徴する感動的なラストシーン。
 あおなみ
あおなみ『セロ弾きのゴーシュ』の重要シーンは、ゴーシュの成長を段階的に描きながら、音楽の「表現力」「リズム」「癒しの力」などを浮かび上がらせます。
ラストの「かっこうへの謝罪」は、彼の内面的な変化を象徴する名場面と言えますね(^^)
『セロ弾きのゴーシュ』の考察や気づき


「宮沢賢治」が『セロ弾きのゴーシュ』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 努力と成長の大切さ
ゴーシュは楽団の中で最も下手なセロ弾きでしたが、毎晩一人で必死に練習し、動物たちとの交流を通して少しずつ成長していきます。
最初は楽長に叱られ続けていた彼が、最後には堂々とした演奏を披露できるようになりました。
この過程は「努力すれば必ず成長できる」というメッセージを象徴していると考えられます。 - 音楽の持つ力(表現・リズム・癒し)
物語の中でゴーシュは「表情がない」「感情がこもっていない」と指摘されますが、動物たちとの交流を通じて音楽の本質を学んでいきます。
特に、カッコウとのやり取りでは「リズムの正確さ」、野ねずみの親子とのエピソードでは「音楽の癒しの力」が描かれています。
宮沢賢治は、音楽が単なる技術ではなく、人の心を動かし、時には病気すら癒す不思議な力を持っていることを伝えたかったのかもしれません。 - 本当の才能とは何か
ゴーシュは最初、楽長に「感情が伝わらない」と言われ、仲間たちからも下手だと思われていました。
しかし、動物たちとの経験を通じて、音楽の持つ意味を理解し、表現力を磨くことで、最終的には素晴らしい演奏を披露できるようになります。
これは「本当の才能とは、もともとの能力ではなく、努力や経験を通じて磨かれるものだ」というメッセージが込められているとも解釈しました。



『セロ弾きのゴーシュ』は、努力することの大切さや、音楽の持つ力、人との関わりの重要性を伝える物語です。
宮沢賢治はこの作品を通じて、 「本当の成長とは、技術だけでなく、心の変化と共に起こるもの」 ということを伝えたかったのではないでしょうか。
宮沢賢治について
① 宮沢賢治とは?
- 生年月日:1896年(明治29年)8月27日
- 出身地:岩手県花巻市
- 職業:詩人・童話作家・農業指導者
- 代表作:『銀河鉄道の夜』『風の又三郎』『注文の多い料理店』など
賢治は、幼い頃から文学や音楽、宗教に深い関心を持ち、農業にも強い興味を抱いていました。特に、仏教(法華経)の影響が強く、人々を救うことや、自然との調和を大切に考えていました。
② 賢治とゴーシュの共通点
1. 音楽への情熱
宮沢賢治は、生涯を通じて音楽を愛していました。彼自身、チェロを演奏していたと言われており、『セロ弾きのゴーシュ』の主人公・ゴーシュと重なる部分があります。
賢治は作曲も行っており、彼の詩には楽譜がついているものもあります。音楽を通じて感情や世界観を表現しようとした点は、作品にも反映されています。
2. 努力と成長の物語
賢治は、地元の裕福な家に生まれましたが、父親の期待に反発し、独自の道を歩みました。
特に、農業指導者としての活動では、農民たちと共に働きながら、農業技術の向上を目指しました。しかし、最初は思うように受け入れられず、苦労したことが記録されています。
これは、楽団の中で下手だとされ、努力しながら成長していくゴーシュの姿と重なります。
3. 自然や動物との共生
賢治の作品には、動植物が重要な役割を果たすことが多く、『セロ弾きのゴーシュ』でも、猫・カッコウ・狸・野ねずみといった動物たちがゴーシュの成長を助けます。
賢治自身、自然を深く愛し、農業や環境保護にも関心を持っていました。動物たちとの交流を通じて人間が学ぶというテーマは、彼の価値観が反映されたものだと考えられます。
③ 賢治の価値観が表れるテーマ
1. 音楽と魂の成長
賢治は、「音楽は人の魂を磨くもの」と考えていました。ゴーシュが動物たちとの交流を通じて演奏の本質を学んでいく過程は、「音楽を通じた自己成長」を描いているとも言えます。
2. 他者との関わりの大切さ
ゴーシュは最初、一人で練習し、自分の問題に気づきませんでした。しかし、動物たちの指摘を受け入れることで成長します。これは、「人は他者との関わりの中で成長する」という賢治の考えを反映していると考えられます。
3. 「本当の豊かさ」とは?
賢治は、単なる成功や名声ではなく、**「本当に価値のあるものは何か?」**を問い続けた人でした。
ゴーシュも、ただ技術的に上手くなるのではなく、音楽の本質を理解し、人の心を動かせるようになったことで本当の成長を遂げます。
④ まとめ
『セロ弾きのゴーシュ』は、宮沢賢治自身の 音楽への愛・努力による成長・他者との関わりの大切さ などが色濃く反映された作品です。
ゴーシュの成長の過程は、賢治自身が農業や文学、音楽を通じて努力し続けた人生とも重なります。
この物語を読むことで、賢治が伝えたかった「努力の尊さ」「音楽や芸術の力」「人や自然との調和の大切さ」について、改めて考えさせられるでしょう。
『セロ弾きのゴーシュ』のあおなみのひとこと感想



ゴーシュの成長物語は、努力の大切さや音楽の持つ力を感じさせる感動的な作品でした。最初は下手だった彼が、動物たちとの交流を通じて技術だけでなく「音楽の本質」を学び、最後には堂々と演奏する姿に胸が熱くなりました(^^)
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!