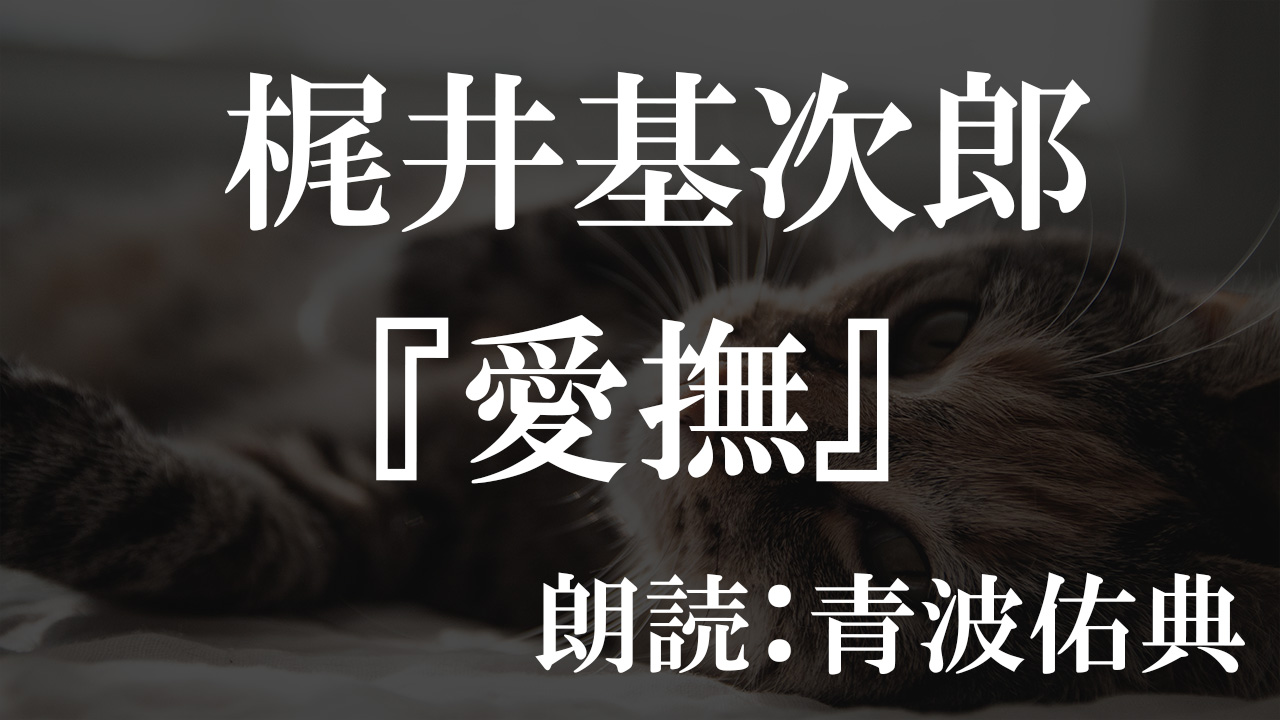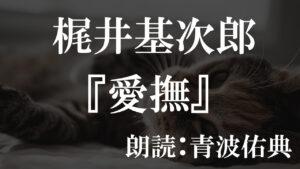猫の耳を「切符切り」で切ってみたい――そんな残酷な空想を抱き続ける男性の物語。
梶井基次郎の「愛撫」は、一見穏やかな猫への愛情を描きながら、人間の心の奥底に潜む異常な欲望を鮮烈に描き出した傑作です。日常に隠された狂気と、愛情に潜む残酷性。
あなたも心当たりがありませんか?
この作品を読めば、自分自身の内面に潜む「もう一つの顔」に気づくかもしれません。
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『愛撫』の物語概要とあらすじ
- 『愛撫』のメッセージや考察
- 『梶井基次郎』について
『愛撫』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
「愛撫」は梶井基次郎による短編小説で、語り手と猫との関係を通して人間の心理や欲望を描いた作品である。
物語は、語り手が子供の頃から猫の耳に対して抱いている奇妙な欲望から始まる。薄べったく冷たい猫の耳を「切符切り」でパチンと切ってみたいという残酷な空想を長年抱き続けている。この欲望は大人になっても消えることがなく、むしろ執念深く心に宿り続けている。
ある日、語り手は猫と遊んでいる最中に、ついに猫の耳を噛んでしまう。すると猫は激しく悲鳴をあげた。この体験によって、語り手は猫の耳が引っ張られることには鈍感だが、噛まれることには非常に敏感だということを発見する。長年の空想はこの瞬間に壊れてしまった。
しかし、一つの空想が消えると、語り手は新たな空想を始める。今度は猫の爪をすべて切り取ってしまったらどうなるかという想像である。爪を失った猫は木登りもできず、飛び跳ねることもできず、次第に自信を失い、恐怖に怯えながら最終的には絶望して死んでしまうのではないかと考える。この空想は語り手を深く悲しませる。
物語の終盤では、語り手がXという女性の夢を見る場面が描かれる。夢の中で、その女性は猫の前足を化粧道具として使って顔に白粉を塗っていた。それは外国で流行している化粧法だと説明される。目覚めた語り手は、実際に猫の前足の柔らかな毛を撫でながら、その感触を楽しむ。最後に、猫を仰向けに寝転がった自分の顔の上に乗せ、猫の前足の裏を自分の瞼に当てて、その温かさと重量に癒されを感じている。
主な登場人物
- 語り手
猫に対して複雑な愛情と欲望を抱く男性。子供の頃から猫の耳に対する奇妙な空想を持ち続けており、大人になってもその執着は消えない。知的で内省的だが、同時に残酷な想像力も持ち合わせている。 - 猫(仔猫)
語り手の愛情と実験的な行為の対象となる動物。耳を噛まれると悲鳴をあげるが、普段は語り手に懐いている。物語を通して語り手の心理状態を映し出す重要な存在。 - X夫人
夢の中に登場する女性。平常時から可愛い猫を飼っており、語り手が訪れると猫を膝から放す。夢の中では猫の前足を化粧道具として使用している。現実と幻想を繋ぐ象徴的人物。 - 謹厳な客
語り手の家を訪れた客人で、膝に上がってきた仔猫の耳を話をしながらしきりに抓んでいた。語り手の猫への欲望を正当化する存在として描かれる。
『愛撫』の重要シーンまとめ

この章では「愛撫」のキーとなるシーンをまとめています。
長年の空想が現実となった瞬間。語り手が猫と遊んでいる最中に、ついに猫の耳を噛んでしまう。猫は即座に悲鳴をあげ、語り手の古い空想は壊れてしまう。この発見により、猫は耳を噛まれるのが最も痛いということが判明する。
新たに生まれた残酷な空想。猫の爪をすべて切り取ったらどうなるかを詳細に想像する場面。木登りができず、飛び跳ねることもできない猫が、次第に自信を失い、恐怖に怯えながら最終的に絶望して死んでしまうという悲劇的な結末を描く。
X夫人が猫の前足を化粧道具として使用している夢のシーン。外国で流行しているという設定で、現実と幻想の境界を曖昧にする。語り手の猫への愛情と利用願望が混在した複雑な心理を表現している。
 あおなみ
あおなみこれらのシーンは、人間の愛情に潜む残酷性と、日常に隠された異常性を鮮やかに描き出している。
『愛撫』の考察や気づき


「梶井基次郎」が『愛撫』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 愛情と残酷性の表裏一体
作者は猫への愛撫を通して、人間の愛情には必ず残酷性が伴うことを示している。語り手の猫への愛情は純粋でありながら、同時に猫を傷つけたいという欲望も含んでいる。これは人間関係における支配欲や所有欲の本質を暗示している。 - 日常に潜む異常性
平凡な日常の中に潜む人間の異常な欲望や空想を描くことで、表面的には正常に見える人間の内面の複雑さを浮き彫りにしている。誰もが心の奥底に抱えている暗い衝動を、猫との関係を通して表現している。 - 孤独な個人の内的世界
語り手の一人称による独白形式により、現代人の孤独な内面世界を描き出している。他者との関係においても、結局は自分自身の欲望や感情の投影でしかないという人間存在の本質的な孤独を表現している。



これらの考察を通して、梶井基次郎は人間の心理の奥深さと複雑さを、猫という身近な存在を媒介として巧みに描き出している。
梶井基次郎について
梶井基次郎(1901-1932)は大正から昭和初期にかけて活動した日本の小説家である。31歳という若さで肺結核により世を去ったが、短い創作期間の中で「檸檬」「城のある町にて」など、独特の感性と文体で知られる秀作を残した。
「愛撫」においても、梶井の特徴である繊細な感覚描写と内省的な文体が存分に発揮されている。猫の耳の質感を「竹の子の皮のように」「硬いような、柔らかいような」と表現する独特の比喩は、まさに梶井文学の真骨頂である。また、日常の些細な出来事から人間の深層心理を掘り下げていく手法は、後の私小説や心境小説にも大きな影響を与えた。
病弱だった梶井にとって、猫のような小さな動物との触れ合いは、生命力を感じられる貴重な体験だったのかもしれない。この作品に描かれた猫への愛情と残酷性の混在は、死と隣り合わせで生きた作者自身の複雑な生命観の反映とも読める。梶井の作品には常に死の影がつきまとうが、同時に生への強烈な愛着も感じられる。「愛撫」はそうした梶井基次郎の文学世界を象徴する作品の一つといえるだろう。
『愛撫』のあおなみのひとこと感想



猫への愛情を描きながら、その奥に潜む人間の残酷性を鋭く描いた秀作。一見穏やかな日常の中に隠された異常な欲望を、美しい文体で表現する梶井の筆力に圧倒される。特に感覚描写の巧みさは圧巻で、猫の耳の質感や前足の温かさが読者にも鮮明に伝わってくる。
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!