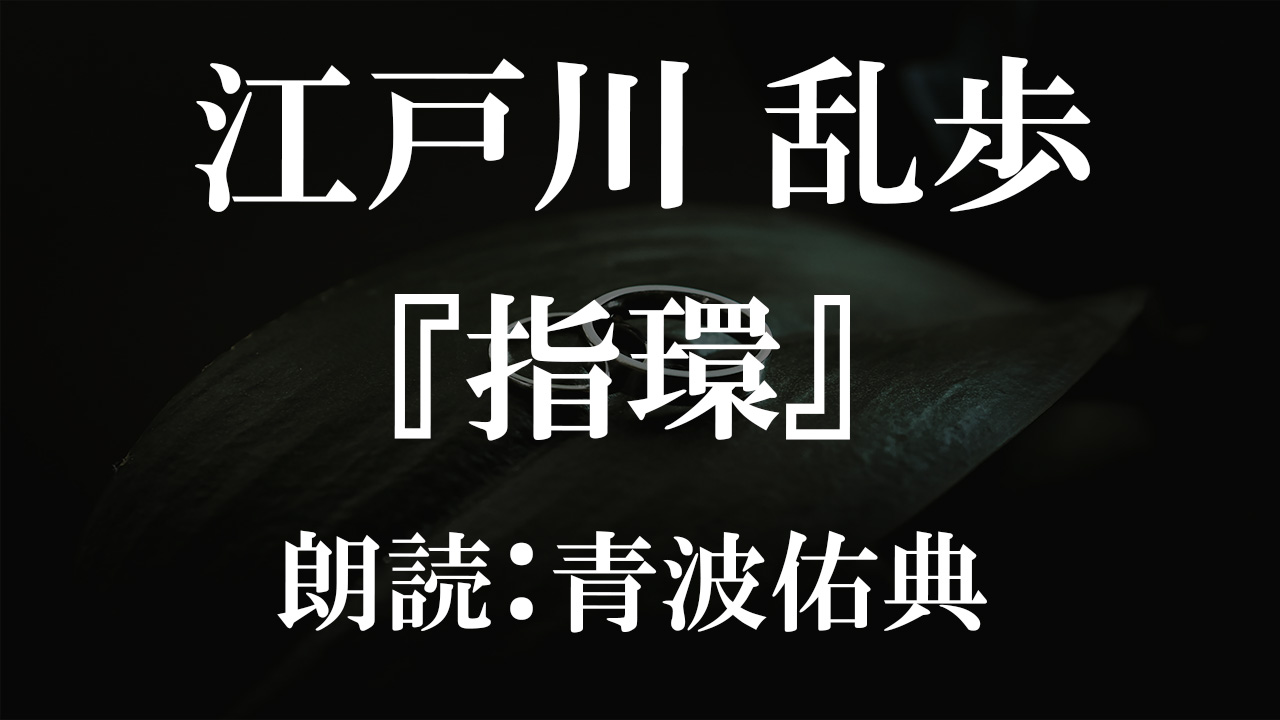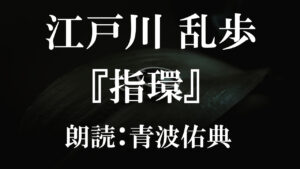江戸川乱歩の短編 『指環』 は、知略と心理戦が交錯する巧妙なミステリーです。
列車内で起こった指環盗難事件。
疑われた男Bは、完璧なアリバイを持ち、誰もが「無実」と思うが……彼の真の狙いとは?
蜜柑に隠された巧妙なトリック、そして予想外のどんでん返し!
最後には、思わず「やられた!」と唸ること間違いなし。
本記事では、あらすじ・重要シーン・考察を深掘りし、乱歩の魅力を余すことなくお届けします!
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『指環』の物語概要とあらすじ
- 『指環』のメッセージや考察
- 『江戸川乱歩』について
『指環』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
ある日、列車の中で偶然に再会した二人の男、AとB。
AはBに対し、以前も同じ列車で出会ったことを指摘する。
Bもそれを思い出し、二人は会話を交わし始める。
以前の旅では、Bが一袋の蜜柑を持ち込み、Aにも分け与えた。
その何気ないやり取りの中で、事件が起こる。
隣の一等車から興奮した乗客たちが流れ込み、そのうちの貴婦人がBを指さし、何やら車掌に囁いたのだ。
車掌はBに声をかけ、貴婦人のダイヤの指環を盗んだのではないかと疑いをかける。
しかし、Bは落ち着き払った態度で「そんなはずはない」と堂々と否定し、自ら身体検査を受け入れる。
車掌や貴婦人の夫までもが執拗にBの体を調べるが、どこを探しても指環は出てこなかった。
Bへの疑いは晴れたものの、乗客たちは彼を怪しげな目で見続ける。結局、指環は見つからず、事件は謎のまま終わったかに見えた。
Aは事件の不可解さについて改めて語るが、Bは突然笑い出し、茶化すような態度を取る。
そして、突如として「しらばくれるのはやめようじゃないか」とAに告げる。
Aもそれを受け、「やはりそうだったのか」と呟く。
二人は互いの腹の探り合いを始め、BはAの狡猾さを指摘する。
事件の最中、Bが蜜柑の袋を窓から投げたのを見たAは、その蜜柑の中に指環が隠されていると推測し、後から拾いに行ったのだった。
しかし、Aが見つけた蜜柑はただの腐った果実ばかりで、指環はなかった。
では、指環はどこへ消えたのか。
Bは種明かしを始める。
彼が蜜柑を窓から投げたのは、実は単なる囮だった。
周囲の注意を蜜柑へ向けさせることで、指環を持っていないと思わせ、身体検査をかいくぐる作戦だったのだ。
そして、本当に指環を隠した場所は、なんとAの腰に下げていた煙草入れの底だった。
Aはまったく気づかないまま、Bの隠れ蓑となっていたのだ。
Bはさらに続ける。
「お前が慌てて蜜柑を拾いに行こうとした時、俺が指環を取り返したんだよ」と。
Aは驚愕し、自分が完全にBにしてやられたことを悟る。
Bの大胆かつ巧妙な策略により、指環は完璧に隠蔽され、Aもまんまと利用されていたのだった。
物語は、Bの高笑いとAの悔しげな沈黙の中で幕を閉じる。
Bの機転の利いた策略と、Aの策士ぶろうとするも一歩及ばなかった姿が、見事なコントラストを生み出している。
主な登場人物
- A(語り手)
物語の進行役となる人物。
Bと列車内で再会し、過去の出来事を振り返る。
かつての事件で、Bがダイヤの指環を盗んだのではないかと疑うが、最終的にはBの策略にはまっていたことを知る。かなりの観察眼を持ち、Bの行動を鋭く見抜くが、最終的にはBに一歩及ばなかった。 - B(狡猾な盗賊)
列車内でダイヤの指環を盗んだと思われる男。
貴婦人の指環を巧妙に盗みながらも、見事に身体検査をかいくぐり、証拠を残さず逃げ切る。
蜜柑を窓から投げることで周囲の注意を逸らし、Aの煙草入れに指環を隠すなど、緻密な計算のもとに行動する。
最終的にAの行動をも予測し、完全に勝利を収める。 - 貴婦人(被害者)
列車の一等車に乗っていた女性。自分の指環が盗まれたことに気づき、Bを疑って車掌に報告する。
夫とともにBを厳しく問い詰めるが、証拠が見つからず戸惑う。 - 貴婦人の夫
貴婦人の指環が盗まれたことでBを強く疑う男性。
Bに執拗な身体検査を行うが、指環が見つからず悔しがる。 - 車掌
事件が起こった際にBを取り調べた列車の車掌。
乗客の証言をもとにBを疑い、厳しく身体検査を行うが、何も発見できず困惑する。
職務に忠実でありながらも、Bの策にはまってしまう。
『指環』の重要シーンまとめ

この章では「指環」のキーとなるシーンをまとめています。
列車の中でAとBが再会する。
Aは以前、同じ列車内でBと出会ったことを思い出し、事件を振り返る。
ここで我々はBが何か過去に問題を起こしたらしいことを察知する。
隣の一等車から貴婦人が興奮した様子でBを指さし、車掌に何かを囁く。
車掌がBに「あなたがダイヤの指環を盗んだのでは?」と問い詰める。
Bは落ち着き払い、「そんなことはない」と潔白を主張する。
車掌や貴婦人の夫がBの体を徹底的に調べる。
口の中や耳の穴まで検査されるが、指環は見つからない。
Bは冷静に振る舞い、疑いは徐々に晴れていく。
しかし、指環は依然として行方不明であり、事件の謎が深まる。
Bは突然、蜜柑の袋を窓から投げ捨てる。
Aはこれを目撃し、「指環を蜜柑の中に隠したのでは?」と考える。
Aは後から蜜柑を拾いに行くが、中には指環は入っておらず、ただの腐った蜜柑だった。
Bは蜜柑を囮にして、指環を隠していたことが示唆されるが、真相はまだ明らかにされない。
BはAに「しらばくれるのはやめよう」と言い、事件の裏側を語り始める。
蜜柑を投げたのは単なる陽動作戦であり、本当に指環を隠したのは別の場所だったと明かす。
Aは驚きつつも、Bがどこに指環を隠したのか理解できていない。
Bは、「指環をお前の煙草入れの底に隠していた」と明かす。
Aは、自分が全く気づかないうちにBの隠れ蓑となっていたことに愕然とする。
さらに、Aが蜜柑を拾いに行こうと慌てていた隙に、Bが指環を取り戻していたことも暴露される。
Aは完全にBに敗北したことを悟り、Bの策略の見事さに打ちのめされる。
Bは大笑いしながら、自分の勝利を確信する。
Aは悔しさを滲ませつつ、何も言い返せない。
物語は、Bの圧倒的な知略と、Aの完敗という形で幕を閉じる。
 あおなみ
あおなみBの巧妙な盗みの手口と、それを知りながらも後手を踏んだAの敗北劇が中心になっていますね。
特に、「蜜柑を投げるシーン」と「煙草入れに指環を隠していたという種明かしのシーン」は、物語のクライマックスとなり、強い印象を残しました(^^)
『指環』の考察や気づき


「江戸川乱歩」が『指環』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 知略と駆け引きの魅力
この作品の最大の魅力は、知恵と策略をめぐる攻防戦です。
Bは、警戒されながらも巧みに証拠を隠し、相手の心理を利用して逃げ切る。
Aもまた、Bの動きを鋭く観察し、一歩先を読もうとするが、結局はBの方が上手だった。
知恵を巡らせ、相手の行動を先読みしながら戦う姿は、単なる盗賊と追跡者の話ではなく、策略と機転の妙を読者に楽しませるものとなっています。
乱歩は、このような頭脳戦の面白さを伝えたかったのではないでしょうか。 - 人間の思い込みと心理トリック
この物語では、人間の思い込みがいかに危ういかが描かれています。
Aは「指環は蜜柑の中にある」と思い込んでいたため、それ以外の可能性を考えられなかった。
車掌や貴婦人の夫も、Bを疑うあまり、彼の策略には気づけなかった。
一方で、Bは相手の思い込みを利用し、意識をそらすことで逃げ切った。
このように、「人は自分が信じたいものを信じる」という心理の盲点が描かれており、乱歩はそれを巧みに物語のトリックに利用しています。 - 直感や感情に流されず、冷静に行動する
物語の中で、AはBの策略に気づきながらも、焦って行動したためにBに一歩先を越されました。
一方のBは、窮地に陥りながらも、常に冷静であり、相手を誘導する余裕すら持っていました。
日常の人間関係おいても、感情的に反応するのではなく、一歩引いて考えることで、より良い解決策を見つけられるではないかと思いました。



この物語を読んで「ただのミステリー」として終わらせるのではなく、日常の中で知恵を活かし、賢く立ち回るヒントにしていけたら、より充実した人生を送ることができるではないかと思いました(^^)
江戸川乱歩について
江戸川乱歩(1894-1965)は、日本の推理小説の礎を築いた作家の一人であり、日本に本格的なミステリー文化を根付かせた人物です。
彼の名前は、アメリカの推理作家エドガー・アラン・ポーに由来しており、ポーの影響を受けた怪奇的・幻想的な作風が特徴的です。
彼の作風は大きく分けると以下のような三つの傾向があります。
- 本格推理小説(論理的なトリックを駆使するもの)
- 『D坂の殺人事件』
- 『屋根裏の散歩者』
- 『心理試験』 など
- 変格探偵小説(怪奇・幻想・異常心理を扱うもの)
- 『パノラマ島奇談』
- 『陰獣』
- 『孤島の鬼』 など
- 少年向け探偵小説(明智小五郎シリーズなど)
- 『怪人二十面相』
- 『少年探偵団』シリーズ など
『指環』は上記の中でも「本格推理」と「変格探偵小説」の中間にある心理戦ミステリーに分類できるでしょう。
2. 『指環』に見る乱歩らしさ
『指環』には、江戸川乱歩の作風の特徴が色濃く表れています。
① 心理戦と策略
乱歩は、トリックそのものよりも「人間の心理」に焦点を当てる作風を好んでいました。
『指環』では、事件そのものは単純(指環の盗難)ですが、**「どのように盗みを隠すか」「どのように相手を欺くか」**という心理戦が物語の本質になっています。
特にBは、Aの考えを読んで蜜柑を囮にするなど、単なるスリではなく、相手の心理を巧みに利用する知能犯です。これは、乱歩が描く「狡猾で知的な犯罪者像」の典型とも言えるでしょう。
② どんでん返しと意外な結末
乱歩の作品では、読者の予想を裏切る結末が特徴です。
- 『屋根裏の散歩者』では、殺人計画が思わぬ形で露見する。
- 『心理試験』では、犯人の計算が狂い、意外なミスから破滅する。
『指環』でも、Bの策略によってAが敗北するという、読者の想像を超えた逆転劇が展開されます。この「最後にすべてがひっくり返る」という構成は、乱歩作品の魅力の一つです。
③ 善悪の曖昧さ
乱歩は、しばしば犯罪者に対して肯定的な視点を持っていました。
- 『指環』でも、AはBを追い詰めようとするが、最終的にBの方が上手であり、読者はBの知恵に驚嘆してしまう。
- つまり、犯罪は悪であるはずなのに、Bの巧妙な手口にはある種の「美学」を感じるのです。
これは乱歩の他の作品にも共通するテーマであり、『陰獣』や『孤島の鬼』などでは、犯罪者が単なる悪ではなく、異常な情熱や才能を持った存在として描かれることが多いです。
3. 乱歩と「犯罪者の知能」への興味
江戸川乱歩は、犯罪者の心理や知能に強い関心を持っていました。
『指環』では、犯罪を成功させるには、警察や周囲の人間の心理を逆手に取ることが重要であることが描かれています。
これは、『心理試験』などの作品にも共通するテーマで、乱歩は**「犯罪とは、単なる暴力ではなく、知能と戦略のゲームである」**と考えていたように思えます。
また、乱歩は探偵小説だけでなく、実際の犯罪にも興味を持ち、戦後の日本の犯罪を分析する評論も書いています。彼は単に物語を書くだけでなく、犯罪心理学的な視点から「なぜ人は犯罪を犯すのか?」を深く考察していました。
4. 乱歩の作品が持つ「遊び心」
『指環』には、真剣な心理戦がありながらも、どこか**「悪ふざけ」のような軽快さ**があります。
- Bは終始余裕を見せ、最後には高笑いする。
- Aはまんまと騙され、読者は「やられた!」という気持ちになる。
このような知的な遊び心は、乱歩の多くの作品に共通しており、彼のミステリーが単なる「暗い犯罪もの」ではなく、読者を楽しませるエンターテイメントになっている理由でもあります。
5. 『指環』が示す乱歩の「知的犯罪者観」
乱歩の作品には、探偵だけでなく、魅力的な犯罪者がしばしば登場します。
- 明智小五郎シリーズでは、「怪人二十面相」が登場し、変装や策略を駆使して警察を翻弄します。
- 『陰獣』では、主人公自身が犯罪者の罠にはまり、狂気の世界へと引きずり込まれます。
『指環』のBも、知的で冷静な犯罪者の典型であり、乱歩の描く「悪の美学」を体現しています。
- 彼は力ずくで盗みを働くのではなく、心理戦を仕掛け、相手を巧みに欺く。
- 最後は高笑いしながら、Aを完全に敗北させる。
このような「知的な悪役」を乱歩は好んで描き、単なる勧善懲悪ではない「頭脳戦としてのミステリー」を作り上げたのです。
『指環』のあおなみのひとこと感想



江戸川乱歩の『指環』は、単なる盗難事件ではなく、知略と心理戦が交錯する巧妙なミステリーでした!
特にBの策略は見事で、読者はAとともに「やられた!」と驚かさました。
知的な駆け引きが光る、痛快な短編ですね(^^)
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!