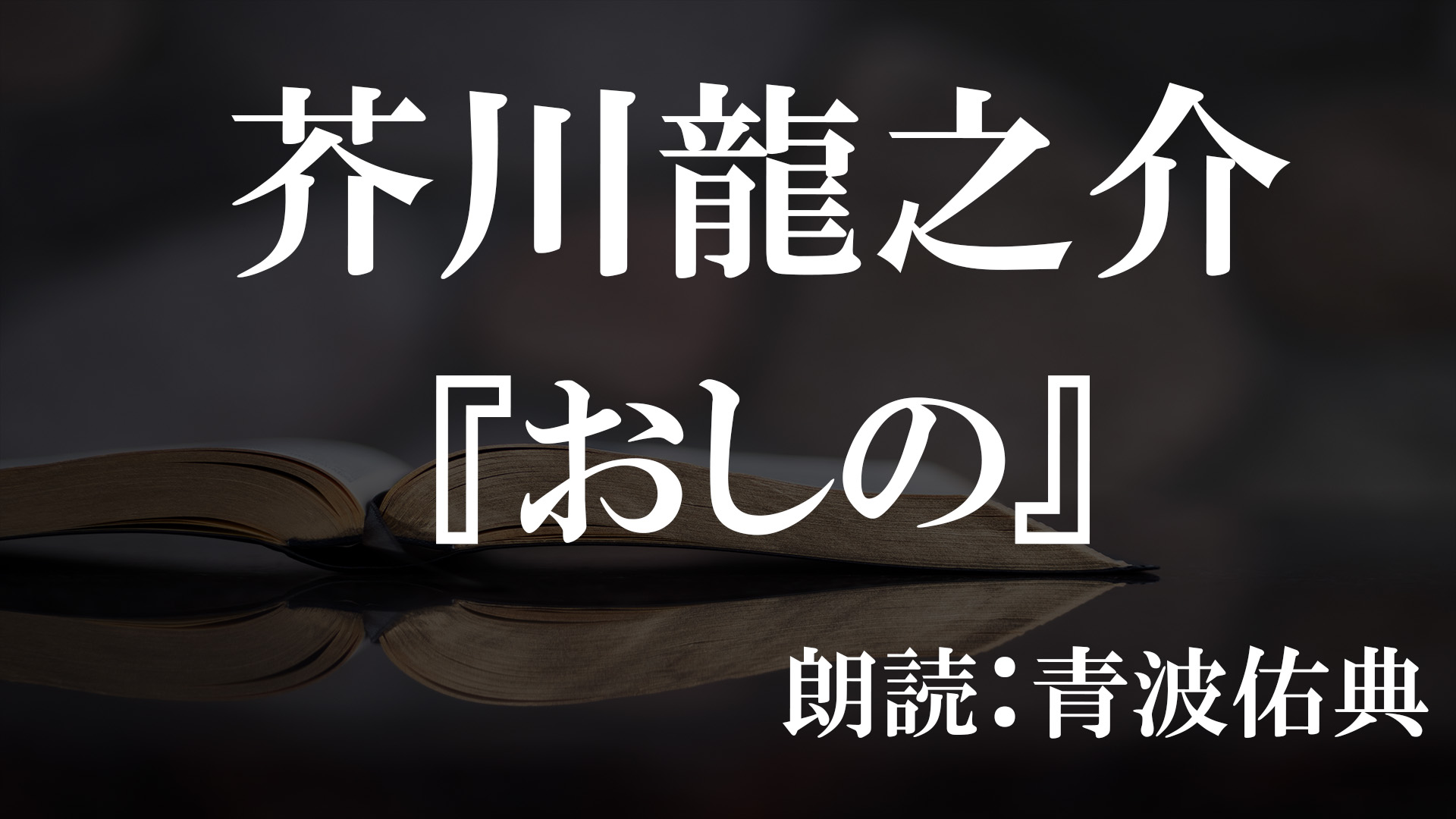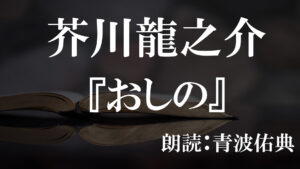「信仰」と「誇り」、あなたならどちらを選びますか?
芥川龍之介の短編『おしの』は、武士の妻・しのと南蛮寺の神父の対話を通して、異なる価値観が交わらないまま衝突する様を描いた物語です。
母として子を救いたい気持ちと、武士の誇りを守りたい信念。しのが最後に下した決断とは——?
本記事では、『おしの』のあらすじや重要シーンをまとめ、芥川がこの作品に込めたメッセージを深掘りします。
思わず考えさせられるテーマと衝撃の結末を、一緒に紐解いていきましょう。
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『おしの』の物語概要とあらすじ
- 『おしの』のメッセージや考察
- 『芥川龍之介』について
『おしの』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
物語の舞台は、薄暗い南蛮寺の堂内。
異国情緒漂う静寂の中、紅毛人(西洋人)の神父が一人、静かに祈りを捧げている。
彼の名は明かされていないが、年齢は四十五、六歳ほど。頬髭をたくわえ、修道服をまとった厳格な人物だ。
そこへ、武家の女房らしき日本人女性が足を踏み入れる。彼女の名は「しの」。
身なりは貧しいが、整った顔立ちの中に険しさを漂わせる女性だ。
彼女は神父に向かい、自らの倅(せがれ)、新之丞(しんのじょう)の病を治してほしいと懇願する。新之丞は十五歳になるが、春頃から重い病に伏せ、あらゆる療養も効果がない。
困窮の末、しのは南蛮寺の医術が「白癩(ハンセン病)」さえ治すと聞き、神父に助けを求めに来たのだった。
神父はその切実な訴えを聞き入れ、新之丞を診ることを約束する。
すると、しのの顔に一瞬、母としての喜びが浮かぶ。その表情に神父は深い感動を覚え、彼女がまるでキリストに乳を含ませた「天上の妃(きさき)」のように見えるのだった。
しかし、しのはこうも言った。
「たとえ病が治らなくとも、あとは清水寺の観世音菩薩にすがるまでです」と。
だが、この言葉が神父の怒りを買う。彼は仏像を「偶像」にすぎないとし、「まことの神は唯一、ジェズス・キリストだけである」としのを諭す。
さらに、キリストが如何に苦しみながらも人々の罪を贖ったのかを熱心に語り、堂内のステンドグラスに映る磔刑のキリストを指し示す。
神父の語るキリストの受難――処女マリアの懐妊、誕生、迫害、奇跡、弟子たちとの最後の晩餐、そして磔刑に至るまで――しのはじっと聞き入る。
しかし、キリストが十字架の上で「エリ、エリ、ラマ・サバクタニ(我が神、我が神、なぜ私を見捨て給うのか)」と叫んだことを聞いた瞬間、彼女の態度が一変する。
しのの夫、一番ヶ瀬半兵衛は、勇敢な武士だった。戦の折には、鎧兜さえ奪われた身であっても、素肌に紙の羽織を纏い、敵陣へと果敢に切り込んだ。
決して敵に背を見せることなく、武士としての誇りを貫いた。そんな夫の妻として、しのは確信する。「臆病者の宗旨に何の価値があろうか」と。
「磔刑の苦しみに耐えかねて神に泣き言を漏らすとは、情けないことだ。臆病者の流れを汲む神父に、わが子を診てもらうわけにはいかない!」
しのは怒りと軽蔑に満ちた目で神父を睨みつけると、さっさと堂を後にする。その姿を呆然と見送る神父の心には、言葉にできぬ衝撃が残ったのだった。
――勇敢な武士の妻としての誇り、母としての愛、信仰の対立が生み出した、この衝撃的な結末。
神父としのの間に交わされた言葉の応酬は、単なる宗教の違いを超え、価値観と信念の衝突を鋭く浮かび上がらせるのだった。
主な登場人物
- しの
武士・一番ヶ瀬半兵衛の後家(未亡人)。 倅(息子)の新之丞が病に伏せており、南蛮寺の神父に治療を求めに来る。 - 神父(紅毛人の司祭)
南蛮寺に仕える西洋人のキリスト教司祭。 祈祷を捧げているところへ、しのが訪ねてくる。 - 新之丞(しんのじょう)
しのの息子で、15歳。 重い病にかかっており、母しのが神父に治療を頼みに行く。 - 一番ヶ瀬半兵衛(いちばんがせ はんべえ)(回想のみ登場)
しのの夫で、佐々木家に仕えた浪人。 戦では敗北して鎧兜を失ったが、それでも命を懸けて戦い抜く勇猛な武士だった。
『おしの』の重要シーンまとめ

この章では「おしの」のキーとなるシーンをまとめています。
堂内で祈る神父の前に、しのが現れる。
彼女は倅・新之丞が重病であることを伝え、神父の医術で助けてほしいと懇願する。
しのは、「もし倅が助からなくても、最終的には観世音菩薩の御加護にすがるつもりだ」と口にする。
これを聞いた神父は、仏教の信仰を「木や石の偶像崇拝」と断じ、「まことの神は唯一、ジェズス・キリストだけだ」と強く非難する。
神父は、イエス・キリストがいかに苦しみながらも人々の罪を贖ったのかを熱弁する。
彼はステンドグラスに映る磔刑のキリストを指し示し、「彼がどれほどの苦難を背負ったか考えてほしい」と語る。
しのは毅然とした態度で、「そんな臆病者の宗旨に何の価値があるのか」と神父を断じる。
彼女は、自らの夫・半兵衛が戦場でどれほど勇敢に戦い抜いたかを語り、「敵に背を向けることなく死んだ夫こそ誇り高い」と主張する。
「臆病者の薬を飲ませるよりは、倅も腹を切るだろう」と言い放ち、憤りと共に堂を後にする。
 あおなみ
あおなみ最終的に、しのは倅の治療を諦め、信仰を捨てるどころか、キリスト教を「弱者の宗教」として軽蔑し、南蛮寺を去る。
この衝突は、単なる「宗教の違い」ではなく、「価値観の衝突」として強烈に描かれているのが、この作品の大きな魅力です。
『おしの』の考察や気づき


「芥川龍之介」が『おしの』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 人は他者の価値観を本当には理解できない
神父はキリストの愛と救済を説き、しのを導こうとする。しかし、しのにはその価値がまったく響かない。それどころか、最後には軽蔑に変わる。
神父は「しののため」に語るが、彼女の価値観を理解しようとしない。
しのは「夫の誇り」を守るために神父の言葉を拒絶し、彼の信仰を理解しようとしない。
芥川は、「人間は、根本的に異なる価値観を持つ相手を理解することができないのではないか?」という問いを投げかけているように見える。 - 「誇り」とは何か?
この作品において、しのが最も重視するのは「誇り」だと感じました。
夫・半兵衛の誇り:「戦場で敵に背を見せず、堂々と戦い抜いた武士」
しの自身の誇り:「武士の妻として、夫の名誉を汚さぬ生き方」
息子・新之丞の誇り:「武士の子として、臆病者の薬を飲むよりも死を選ぶべき」
しのにとって、「誇り」とは生き方そのものであり、それを失うことは「死」以上に意味のないことだった。そのため、キリストの磔刑における「神への嘆き」は、彼女にとって受け入れがたいものだった。 - 「押しつけ」では人は変えられない
神父は善意からキリスト教の教えを説きましたが、しのには「押しつけ」としか映らず、結果的に拒絶されました。この構図は、現代のコミュニケーションでもよく見られます。
✅ 自分の意見を強く押しつけても、相手の価値観が変わるとは限らない。
✅ 人は、自分自身が納得しない限り、考えを変えない。
✅ 相手の立場を尊重しながら、理解を促すことが大切。



この作品は、単なる宗教の話ではなく、現代社会でも必要とされる「コミュニケーションの本質」や「多様性を受け入れる大切さ」を教えてくれるものです。
私たちも日常の中で、「相手の立場を理解し、尊重すること」を意識することで、より良い人間関係を築くことができるのではないでしょうか。
芥川龍之介について
『おしの』を読み解く上で、芥川龍之介(1892-1927)の生涯や思想を知ることはとても重要です。この作品に込められたテーマや視点は、彼の宗教観や異文化に対する考え方と深く結びついています。
1. 芥川龍之介の宗教観
芥川は生涯にわたって宗教に強い関心を持っていましたが、特定の信仰に帰依することはありませんでした。仏教、キリスト教、神道などの宗教を題材にした作品を多く書いていますが、それらを単純に肯定するのではなく、常に「懐疑の目」で見ていたのが特徴です。
『おしの』における宗教観
- 神父の視点: 彼は「唯一神」を信じ、仏教を否定する。しかし、その信仰の押しつけが最終的にしのの反発を招く。
- しのの視点: 彼女は武士の誇りを重んじ、キリスト教の価値観を拒絶する。しかし、それは単なる排他ではなく、彼女なりの信念に基づいている。
- 芥川の視点: どちらの信仰も「絶対的に正しい」とは描かれず、むしろ「異なる価値観は交わらない」という現実を示している。
芥川自身は、宗教に救いを求めつつも、それに疑問を抱き続けた人物でした。
彼の代表作『神神の微笑』では、「神の存在を信じながらも、それが人間にどれほどの意味を持つのか」という問いが描かれています。『おしの』も同様に、信仰とは何か、人は本当に他者の信念を理解できるのか、というテーマを投げかけています。
2. 異文化に対する芥川の姿勢
芥川は明治時代末期から大正時代にかけて、日本が西洋文化を急速に取り入れた時代に生きました。彼自身も西洋文学を深く学び、特にロシア文学やフランス文学に影響を受けています。
『おしの』における異文化の対立
この作品では、日本と西洋の価値観の違いが明確に描かれています。
- 神父のキリスト教 = 「愛と忍耐、唯一神を信じることによる救済」
- しのの武士道 = 「誇りと名誉、臆病を恥じる精神」
芥川は、日本が西洋化していく中で、「果たして日本人にとって西洋文化は本当に受け入れられるものなのか?」という疑問を持っていました。『おしの』では、最終的に日本人であるしのがキリスト教を拒絶することで、「価値観の違いは容易に埋まらない」という現実を示しています。
また、芥川は1921年に中国を訪れ、『上海游記』を記しました。そこで彼は「西洋化の進む中国」と「伝統を重んじる中国」の二面性を目の当たりにし、日本の未来にも同じような分裂が訪れるのではないかと考えました。『おしの』は、まさにその問いを反映した作品と言えるでしょう。
3. 芥川龍之介の人生と『おしの』の関連性
芥川の人生を振り返ると、『おしの』のテーマとつながる部分が多くあります。
幼少期の体験
芥川は生後7ヶ月のときに実母が精神を病み、伯母に育てられました。この経験が彼の「生と死」に対する哲学や、「人間はどう生きるべきか?」というテーマを持つ作品に影響を与えました。
しのも、夫を亡くし、倅(せがれ)の命を守るために神父を訪れますが、最終的に信仰の押しつけに反発して去ります。
芥川自身も「自分の人生を導いてくれる存在」を求めながら、それを完全に信じることができなかったのではないか、と考えられます。
知識人としての葛藤
芥川は東京帝国大学で英文学を学び、知識人としての地位を築きました。しかし、彼は「知識が増えるほど、人は不安や迷いを抱える」とも考えていました。これは『おしの』の神父にも通じる部分があります。
- 神父 = 知識を持ち、信仰の正しさを説くが、最終的にしのの反発に遭い、彼女を理解できなかった。
- 芥川 = 西洋文化を学びながらも、それが本当に日本人の心に合うものなのかを疑問に思っていた。
『おしの』の神父のように、芥川も「知識と信念の間で揺れ動く」存在だったと言えるでしょう。
4. 自殺と「人間の救い」
芥川は1927年に自殺しました。『おしの』が発表されたのは1923年(大正12年)で、彼が自殺する4年前です。この時期、芥川は精神的に不安定で、「生きること」や「人間の救済」について深く悩んでいました。
**『おしの』のラストは、まさに「救済の拒絶」**です。
しのは神父の教えを拒み、信仰にすがることなく去っていきます。これは、「人は本当に宗教で救われるのか?」という芥川自身の疑問が投影されているのではないでしょうか。
また、芥川は『歯車』や『河童』といった晩年の作品で「精神的な苦悩」を強く描いています。彼にとって、救済とは「信じることで得られるもの」ではなく、「自分で見出すもの」だったのかもしれません。
『おしの』のあおなみのひとこと感想



『おしの』は、宗教と武士道という価値観の対立を鋭く描いた作品。
神父の説くキリストの「受難」は、しのにとって「臆病な弱音」に映る。
信仰とは何か、価値観は交わり得るのかという問いが浮かび、異文化理解の難しさを痛感させられました。
芥川の冷静な筆致が、単なる宗教論争ではなく、人間の誇りや信念の本質を鮮烈に浮かび上がらせている。
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!