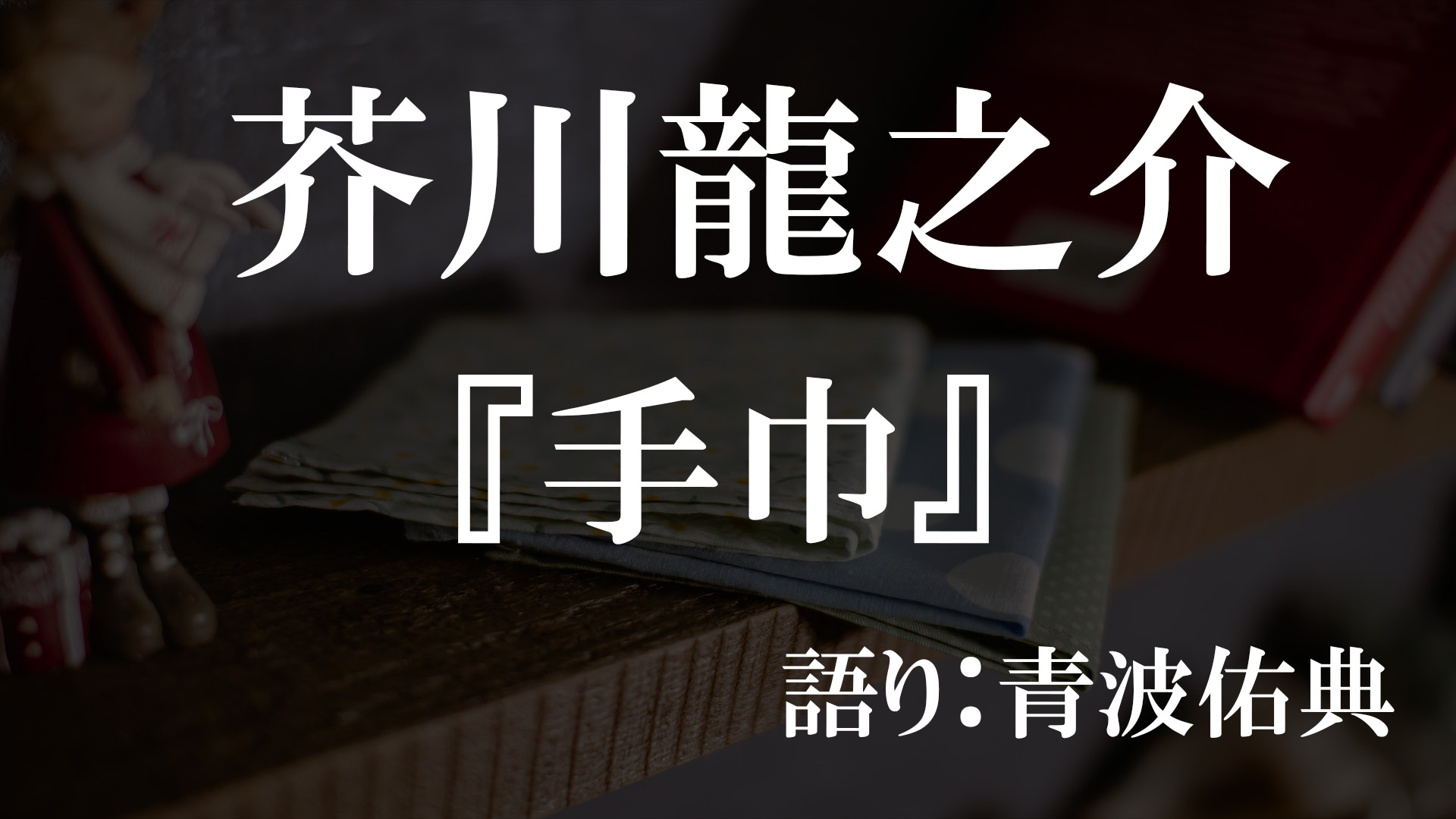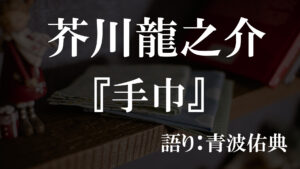「日本人の美徳」とされる、感情を抑えた強さ。それは本当に誇るべきものなのか、それともただの「型」なのか——?
芥川龍之介の短編『手巾(ハンケチ)』は、そんな問いを鋭く投げかける作品です。
ある教授と一人の母親との対話を通して、武士道精神や伝統的価値観の本質に迫る本作。
読後、あなたの「美徳」に対する見方が変わるかもしれません。
この記事では、『手巾』のあらすじ、重要シーン、考察をわかりやすく解説していきます!
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『手巾』の物語概要とあらすじ
- 『手巾』のメッセージや考察
- 『芥川龍之介』について
『手巾』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
物語の主人公は東京帝国法科大学教授の長谷川謹造。
彼は自宅のヴェランダで籐椅子に座り、スウェーデンの劇作家ストリンドベリの作劇術に関する本を読んでいる。
専門は植民政策だが、学生たちが関心を寄せる書物には積極的に目を通す教育熱心な人物である。
ヴェランダには妻が選んだ岐阜提灯が吊されており、長谷川はそれを眺めながら日本文化と西洋文明の融合について思いを巡らせる。特に日本の精神的衰退を憂い、武士道精神がその救済となり得ると信じていた。
そんな静かな午後、使用人が訪問客を告げる。
名刺には「西山篤子」と記されており、長谷川は心当たりがないまま応接室へ向かう。
待っていたのは、上品で落ち着いた中年女性。彼女は長谷川の教え子で、演劇評論を好んでいた西山憲一郎の母親であった。
西山は腹膜炎で入院していたが、先日亡くなったことを伝えるために訪ねてきたのだった。
息子の死を語る篤子は、穏やかで微笑さえ浮かべていた。
その態度に長谷川は違和感を抱くが、やがて彼女が膝の上でハンケチを強く握り、手が震えていることに気づく。
外見では取り乱さないよう努めつつ、内面では深い悲しみと感情の抑制に苦しんでいたのだ。
この瞬間、長谷川は西洋で体験した情景を思い出す。
ベルリン留学中に皇帝の死を子供たちが純粋に泣き悲しんでいた姿と、日本の女性が感情を抑え込む姿勢が対照的であることに考えを巡らせた。
帰宅後、長谷川は夕食を取りながらアメリカ人の妻にこの出来事を話し、日本女性の奥ゆかしさや武士道精神の象徴として篤子の姿を称賛する。
夜、再びヴェランダに座ってストリンドベリの本を開いた長谷川は、そこに「俳優が微笑みながら手巾を裂く二重の演技」の記述を見つける。
その瞬間、篤子が見せた外見の冷静さと内心の激しい感情が「演技」であったかのように感じ、理想としていた武士道と、その「型」にとらわれた振る舞いとの間に違和感を覚える。
物語は、外面的な強さと内面的な悲しみのギャップ、そして道徳や精神論が時に形式化することへの疑念を浮き彫りにしつつ、長谷川が岐阜提灯の灯りを見つめる場面で幕を閉じる。
主な登場人物
- 長谷川謹造(はせがわ きんぞう)
東京帝国法科大学の教授で、植民政策が専門。教育熱心で学生たちの思想や興味に関心を持ち、専門外の書籍も読む。
日本の精神的衰退を憂い、武士道精神を日本の精神的再生の鍵と信じている。 - 長谷川の妻
アメリカ人だが日本文化を愛し、夫と同じく日本の美術工芸を好む。
物語では直接の発言や行動は少ないが、ヴェランダに吊るした岐阜提灯を選んだことや、夫の話に共感を示す姿勢が描かれている。長谷川にとって、西洋と日本文化の橋渡し的存在。 - 西山篤子(にしやま あつこ)
長谷川の教え子・西山憲一郎の母。息子の死を知らせに訪れるが、外見上は冷静で、落ち着いた態度を崩さない。
実は深い悲しみを抱えており、膝上でハンケチを強く握りしめ、内心の激しい感情を抑えている。
日本女性特有の感情抑制と武士道精神を象徴する存在として描かれている。 - 西山憲一郎(にしやま けんいちろう)
長谷川の学生で、演劇評論を執筆する知的な青年。
腹膜炎で入院後、若くして亡くなる。生前は思想問題に関心が強く、長谷川のもとを訪れて議論を交わしていた。
『手巾』の重要シーンまとめ

この章では「手巾」のキーとなるシーンをまとめています。
長谷川はヴェランダでストリンドベルクの作劇術を読みながら、岐阜提灯を眺めて日本文化に思いを巡らせています。
日本は物質的には近代化したものの、精神的な進歩は乏しく、むしろ退廃していると考えます。
その中で「日本精神の再生には武士道が必要」と結論づけます。
訪問した西山篤子は、息子・西山憲一郎の死を淡々と語ります。
長谷川は、息子を亡くした母親とは思えないほどの落ち着きぶりに驚きます。
会話の中で長谷川は偶然、篤子の膝の上の手巾に気づきます。
それが激しく震えており、篤子が感情を必死に抑えていることを理解します。
彼女は顔では笑みを保っていたものの、内面では深い悲しみを抱えていたのです。
篤子とのやり取りの後、長谷川は妻に彼女の「武士道的振る舞い」を語り、日本女性の強さを賞賛します。
しかし、その後ストリンドベルクの本を再び開くと、「俳優が微笑しながら手巾を裂く二重演技」に関する記述が目に入ります。
彼は武士道を「崇高な精神」として尊んでいたものの、その精神が「型」に落ち、無意識の演技として表れることに複雑な感情を抱きます。
 あおなみ
あおなみ『手巾』の核心は、表面的な美徳(武士道的強さ)と内面的な感情の激しさとの間にある矛盾だと感じました。
特に「篤子の手巾を握りしめる場面」が最も象徴的で、長谷川が感じた「尊さ」と「不自然さ」が、読者にも複雑な余韻を残します。
『手巾』の考察や気づき


「芥川龍之介」が『手巾』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 感情の抑制と表現の問題
芥川は、「感情を抑えること」が本当に美徳なのか、「感情を表現すること」が弱さなのかを問いかけます。
外面の平静が実は「演技」に過ぎないのではないかという疑問を通して、人が社会や文化の期待に合わせて自分を偽ることへの皮肉が込められているのではないでしょうか。 - 武士道精神への批判的考察
長谷川は日本の精神的衰退を憂い、武士道こそが救いだと考えていました。しかし、篤子の抑えた悲しみを目の当たりにし、それが「武士道の精神的美徳」なのか、それとも「単なる形式的な演技」なのか迷い始めます。
伝統的な価値観や美徳が形骸化し、本来の精神が失われているのではないかと疑問を投げかけています。
形だけの「型」に縛られることが、むしろ個人の自然な感情や人間らしさを抑えつけるのではないかという批判が感じられます。 - 東洋と西洋の文化的価値観の対比
篤子は日本人らしく感情を抑え、長谷川もそれを武士道的美徳と解釈しました。
一方で、長谷川はベルリン留学中に、ドイツの子供たちが皇帝の死を聞いて素直に泣きじゃくる姿を見ています。
西洋では感情表現が自然で肯定されるのに対し、日本では抑制が美徳とされる矛盾に彼は直面します。
芥川は東洋と西洋の価値観の違いを浮き彫りにしながら、どちらが優れているという単純な結論を出しません。むしろ、「文化の型に人が従うべきか、人間本来の感情を優先すべきか」という普遍的な問いを投げかけています。



表面的な美徳や伝統の重みに疑問を持ちながらも、それを完全には否定しきれない人間の複雑な心情を描き出しているのかもしれませんね。
芥川龍之介について
芥川龍之介と『手巾(ハンケチ)』
芥川龍之介(1892–1927)は、日本の近代文学を代表する作家の一人であり、短編小説の名手として広く知られています。彼の作品には人間の心理の微細な描写、社会への鋭い洞察、伝統と近代の対立といったテーマが繰り返し登場します。『手巾(ハンケチ)』もまた、芥川の文学的特徴が色濃く表れた作品です。
1. 芥川龍之介の背景と『手巾』の関係
① 武士道への関心と批判的視点
芥川は明治期に生まれ、大正・昭和初期に活動しました。この時代、日本は近代化の真っただ中で、西洋文明を急速に取り入れる一方で、武士道や儒教的価値観といった伝統との葛藤がありました。
『手巾』の長谷川は武士道を称賛しますが、最後に「それは単なる型ではないか?」と疑念を抱く──これは、芥川自身が伝統的価値観に対して持っていた複雑な感情を反映しているともいえます。
特に、明治政府によって理想化された「武士道」に対して、芥川は批判的でした。彼は、武士道がもはや生きた精神ではなく、ただの「形式」として残っているのではないかと考えていました。その視点が『手巾』の結末に表れています。
② 西洋文化との関係
芥川は西洋文学や思想に深い関心を持っていました。特にフランス文学やロシア文学、北欧の劇作家(イブセンやストリンドベルク)に強い影響を受けています。
『手巾』の冒頭で、長谷川がストリンドベルクの作劇術を読んでいることも、この影響を示唆しています。
また、芥川は1910年代から1920年代にかけて、西洋の合理主義と、日本の伝統的な情緒との対立を強く意識していました。『手巾』では、西洋では感情を素直に表現するのに対し、日本では感情を抑制する文化が美徳とされることが描かれています。
長谷川がドイツ留学中に、皇帝の死を子供たちが泣いて悲しむエピソードを見て驚く場面は、まさに西洋と日本の感情表現の違いに対する芥川の興味を反映しています。
2. 『手巾』と芥川作品の共通点
① 人間心理の細やかな描写
芥川は、人間の複雑な感情を細やかに描写することに長けていました。『手巾』では、西山篤子の「外面的な冷静さ」と「内面的な激情」の対比が、手巾を握りしめる仕草を通じて描かれます。
これは、彼の代表作である『鼻』『地獄変』『藪の中』などの作品に共通する、「見せかけの態度と本心の乖離」というテーマにも通じています。
② 伝統的価値観への疑問
芥川の作品には、日本の伝統や道徳に対する疑問がしばしば登場します。
『羅生門』では、生きるためには悪をも辞さない人間の姿を描き、『舞踏会』では日本人の西洋かぶれに対する風刺を込めています。
『手巾』では、日本の美徳とされる「感情を抑えること」が本当に正しいのかを問う形になっています。
③ 芸術と現実の関係
『手巾』のラストで長谷川は、ストリンドベルクの本に「俳優が微笑しながら手巾を裂く演技」の記述を見つけます。これは、西山篤子の態度と酷似しており、「彼女の振る舞いは演技ではなかったのか?」という疑念を生み出します。
これは、芥川がしばしば描いた「現実の出来事が芸術とシンクロする瞬間」というテーマにもつながります。
たとえば、『地獄変』では、画家が自分の娘を犠牲にしてまで芸術の完成を求めるという話が描かれます。
『手巾』でも、現実の悲しみが「演技」として見えることで、「私たちが美徳と思っているものも、実は演出されたものではないか?」という疑念が生じるのです。
3. 『手巾』と芥川の晩年
芥川龍之介は1927年に自殺しました。彼の晩年は精神的に不安定で、社会に対する絶望感を強めていました。彼は「人生に対するぼんやりした不安」を抱えていたと遺書に記しています。
『手巾』のラストシーンには、そうした芥川の「現実への疑問」や「価値観の相対化」が色濃く表れています。
長谷川が岐阜提灯の灯りを眺めながら、武士道の「型」に対して不快感を覚える場面は、芥川自身が社会や文化に対して持っていた不安と通じるものがあります。
彼は、「人間が社会のルールや文化の型に従うことは本当に正しいのか?」という問いをずっと持ち続けていました。『手巾』は、その疑問を端的に表現した作品ともいえるでしょう。
『手巾』のあおなみのひとこと感想



『手巾』は、日本的な「感情の抑制」と「武士道精神」の美徳に疑問を投げかける作品だと感じました。
西山篤子の冷静な態度が、実は強い感情の抑圧であることが明らかになる場面は印象的で、社会の期待に応じた「演技」としての振る舞いを考えさせられますね。
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!