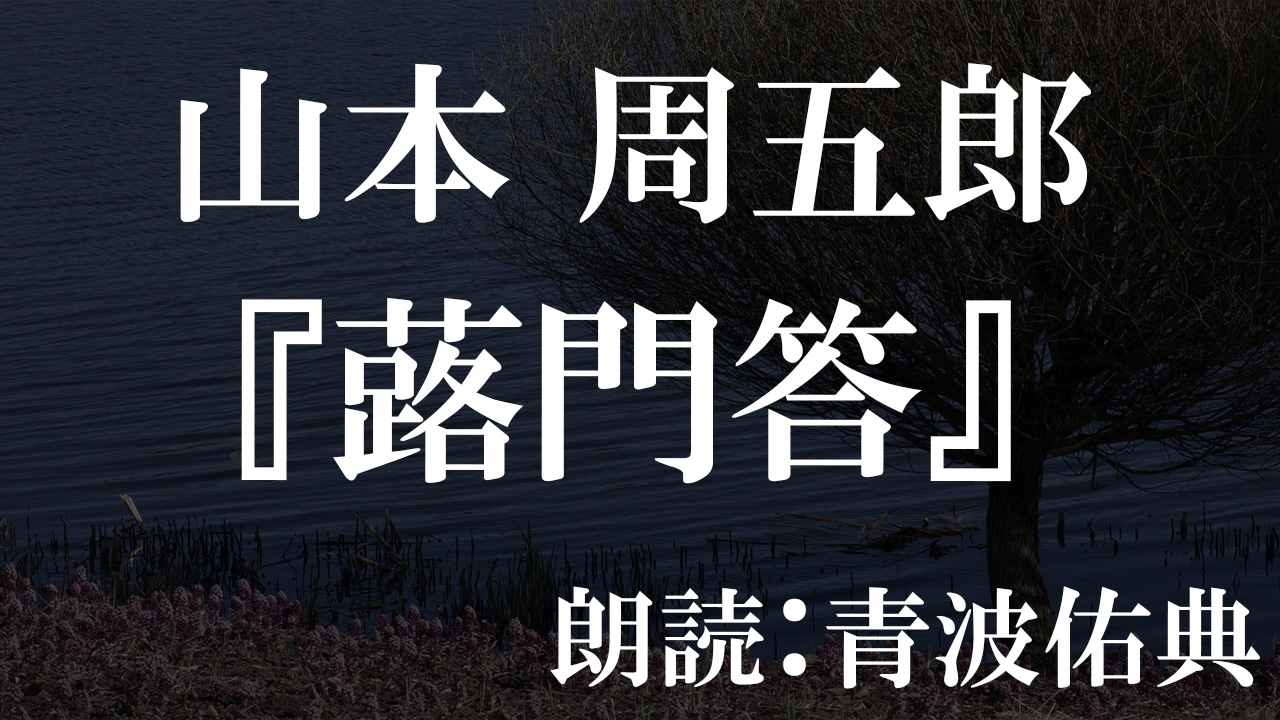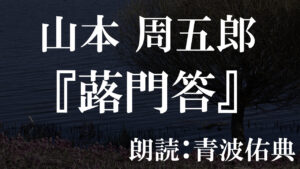健忘家の武士と醜女の意外な夫婦が織りなす、心温まる人間ドラマ。
山本周五郎の「蕗問答」は、外見や欠点で人を判断することの愚かさと、真の価値を見抜く大切さを教えてくれる珠玉の名作です。
笑いの中に深い人間愛が込められたこの物語は、現代を生きる私たちにも重要なメッセージを投げかけています。
完璧でない人間だからこそ愛おしい、そんな普遍的な真理を描いた傑作をぜひご堪能ください。
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『蕗問答』の物語概要とあらすじ
- 『蕗問答』のメッセージや考察
- 『山本周五郎』について
『蕗問答』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
江戸時代、秋田藩士の寒森新九郎は年寄役筆頭という重職に就いているが、極度の健忘家として「忘れ寒森」と呼ばれるほど有名だった。安永六年、藩主佐竹義敦が江戸城で秋田の巨大な蕗を自慢したところ、諸侯に嘘だと笑われてしまう。義敦は実物を取り寄せて見せつけ、面目を保った。
新九郎はこの軽率な行為を諫言するため江戸へ向かうが、途中で肝心の目的を忘れてしまう。義敦に謁見した際、困り果てた新九郎は苦し紛れに側女の浪江(通称「おこぜ」)を妻にしたいと申し出る。義敦は新九郎の窮状を見抜きながらも、意地悪く即座に縁組を承諾し、その場で仮杯を交わさせて帰国させる。
秋田に戻った新九郎は、浪江が本格的に家政を切り盛りし始めることに驚く。彼女は荒地を開墾し、家士たちを督励して農作業に従事させる。さらに秋田の大蕗を砂糖漬けにして江戸で売る商売まで始める。この蕗漬け作りを見た新九郎は、ようやく当初の諫言の目的を思い出す。
再び江戸に出向いた新九郎は、今度は忘れないよう紙に書き留めて準備万端で義敦に諫言する。東照神君の「真らしき嘘は申すもよし、嘘らしき真は申すべからず」という言葉を引用し、義敦の軽率な行為を戒める。義敦は素直に非を認めるが、新九郎の前回の失態を笑い、浪江を返すと申し出る。しかし新九郎は浪江の有能さを認め、正式に妻として迎えることを宣言し、得意満面で物語は終わる。
主な登場人物
- 寒森新九郎
秋田藩士で年寄役筆頭。食禄八百石の重職だが、極度の健忘家として「忘れ寒森」と呼ばれる。強情で圭角が多いが、特異な人徳を持つ。物忘れのために思わぬ展開を招くが、最終的には人を見る目の確かさを示す。 - 佐竹義敦
秋田藩主。江戸城で秋田蕗を自慢して諸侯に笑われ、実物を取り寄せて面目を保つ。新九郎の健忘を見抜いて意地悪な悪戯をするが、最終的には諫言を素直に受け入れる器量を見せる。 - 浪江(おこぜ)
義敦の側女。「おこぜ」という綽名の通り醜女だが、26歳で健康な体と怜悧な頭脳を持つ。愛嬌があり人気者。新九郎の妻となってからは優秀な家政手腕を発揮し、開墾や商売で家計を支える。
『蕗問答』の重要シーンまとめ

この章では「蕗問答」のキーとなるシーンをまとめています。
義敦が江戸城で秋田の巨大蕗を自慢するが諸侯に嘘だと笑われ、実物を取り寄せて見返すという軽率な行為が物語の発端となる。藩の財政逼迫時の不適切な支出として、後に新九郎の諫言の対象となる重要な伏線。
諫言のため江戸に向かった新九郎が途中で目的を忘れ、義敦との謁見で困り果てて浪江との縁組を申し出る場面。新九郎の健忘ぶりと機転、そして義敦の意地悪な性格が絶妙に描かれた、物語最大の山場。
浪江が蕗を砂糖漬けにして江戸で売る商売を始める場面を見て、新九郎が当初の諫言の目的を思い出すクライマックス。忘れていた記憶が蕗という共通項で蘇る、巧妙な構成の妙が光る場面。
 あおなみ
あおなみ人間の記憶とは不思議なもので、思わぬきっかけで大切なことを思い出すものですね。
『蕗問答』の考察や気づき


「山本周五郎」が『蕗問答』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 人間の愛すべき欠点
新九郎の健忘という欠点が、かえって人間的魅力となって周囲に愛される様子を描いている。完璧でない人間だからこそ親しみやすく、その欠点すら人徳の一部となることを示している。現代社会でも、完璧を求めすぎず、欠点も含めて人間を受け入れることの大切さを教えてくれる。 - 権力者の謙虚さ
義敦が最終的に新九郎の諫言を素直に受け入れる姿勢は、真の指導者のあり方を示している。地位や権力に奢ることなく、部下の意見に耳を傾ける謙虚さこそが統治者に必要な資質である。現代の組織運営においても、上司が部下の意見を真摯に受け止める重要性を物語っている。 - 伝統と革新の調和
浪江が伝統的な秋田蕗を新しい商品として江戸で売り出すアイデアは、伝統を活かしながら革新を図る知恵を表している。地方の特産品を都市部で商品化するという発想は、現代の地域活性化にも通じる先見性がある。古いものを大切にしながらも新しい価値を創造する姿勢の重要性を示している。



人間関係の機微を描いた、今読んでも色褪せない名作ですね。
山本周五郎について
山本周五郎(1903-1967)は昭和期を代表する時代小説家で、本名は清水三十六。本作「蕗問答」は彼の代表作の一つで、健忘家の武士を主人公とした軽妙洒脱な作品として知られています。
山本周五郎の特徴は、権力者よりも庶民や市井の人々に温かい眼差しを向けた点にあります。「蕗問答」でも、新九郎という欠点だらけの武士や、醜女として軽視される浪江といった、一見取るに足らない人物たちの人間的魅力と潜在能力を丁寧に描き出しています。
また、彼の作品には「やぶからぼう」「ながい坂」「樅ノ木は残った」など、人間の本質を見つめた名作が多く、特に女性の描写に優れていました。浪江のような、外見は醜くても内面の美しさと能力を持つ女性の造形は、山本文学の真骨頂といえるでしょう。時代小説でありながら現代にも通じる普遍的なテーマを扱い、読者に深い感動を与え続けています。
『蕗問答』のあおなみのひとこと感想



健忘家の新九郎が起こす騒動を通じて、人間の愛すべき欠点や真の価値を見抜く大切さが描かれた傑作です。特に浪江の有能さが徐々に明かされる構成が巧妙で、外見で人を判断することの愚かさを痛感させられます。軽妙な筆致の中に深い人間洞察が込められており、何度読んでも新しい発見がある名作だと思います。
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!