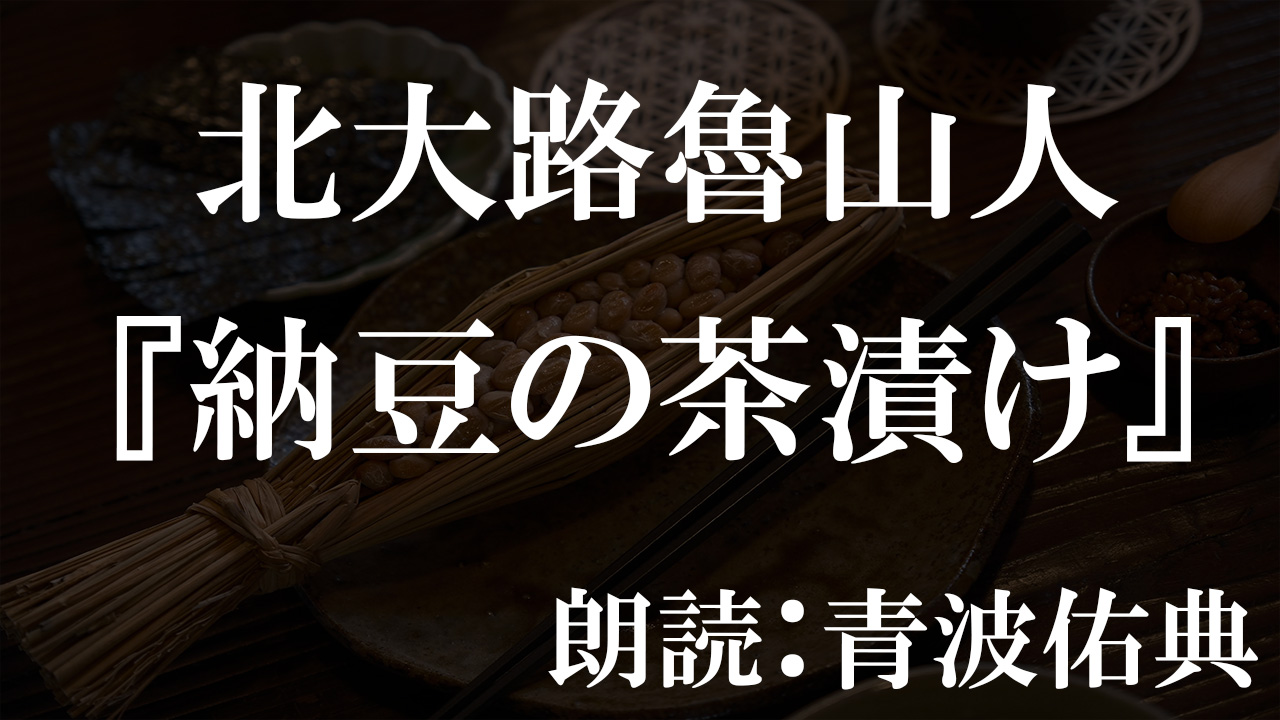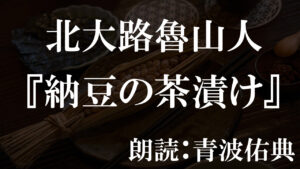「納豆の茶漬けは意想外に美味いものである」
—この一文から始まる北大路魯山人の随筆には、日常食を芸術に昇華させる美食家の哲学が詰まっています。
納豆という庶民的な食材の練り方一つに魂を込め、「糸を出せば出すほど美味くなる」と説く魯山人。
シンプルな料理の中に日本文化の精髄を見出す彼の美意識と、誰も知らなかった「納豆の茶漬け」の魅力を、あなたも一緒に味わってみませんか?
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『納豆の茶漬け』の物語概要とあらすじ
- 『納豆の茶漬け』のメッセージや考察
- 『北大路魯山人』について
『納豆の茶漬け』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
北大路魯山人による随筆「納豆の茶漬け」は、あまり知られていない食べ方である納豆の茶漬けについて、その魅力と正しい作り方を詳しく解説した作品です。
作者は冒頭で、納豆の茶漬けが「意想外に美味いもの」であるにも関わらず、食通の間でさえ知る人が少ないことに驚きを示しています。
そして、本文では納豆の正しい「拵え方(こしらえかた)」について詳細に説明しています。
まず、納豆は何も加えず二本の箸でよく練り混ぜることから始めます。
練れば練るほど納豆から出る糸が増え、これが納豆の美味しさを引き出すのだと説きます。
十分に練り上げた後、少量ずつ醤油を加えながら練り続け、最終的に糸が見えなくなるまで丁寧に作業します。
好みによって辛子や薬味(ねぎのみじん切り)を加えると、さらに味が引き立つとしています。
次に、茶漬けの作り方について解説しています。茶碗に熱い飯を少量盛り、その上に調理した納豆を適量のせて煎茶をかけるだけの簡単な料理法です。
納豆は飯の四分の一程度が最も美味しく、少なすぎると味が悪く、多すぎると食感が煩わしくなると注意しています。
また、納豆の良し悪しについても言及しており、糸を引かない発酵不十分な納豆は美味しくないとしています。
理想的な納豆は豆の質が細かく、ねちねちとした食感のものだと記しています。
特に仙台や水戸などの小粒の納豆を推奨しています。
最後に、この料理が簡単に作れるものであることを強調し、秋の美味しい食べ物として試してみることを勧めて締めくくっています。
この随筆全体を通して、魯山人特有の繊細な味覚と、料理に対する真摯な姿勢、そして何気ない日常食を芸術レベルまで高める美食家としての哲学が感じられる作品となっています。
主な登場人物
- 北大路魯山人(きたおうじ ろさんじん)
本作の著者。美食家・芸術家として知られ、料理や食器、書画などの芸術に造詣が深い。本作では納豆の茶漬けという一見シンプルな料理について、その美味しさと正しい作法を伝える語り手として登場している。
『納豆の茶漬け』の重要シーンまとめ
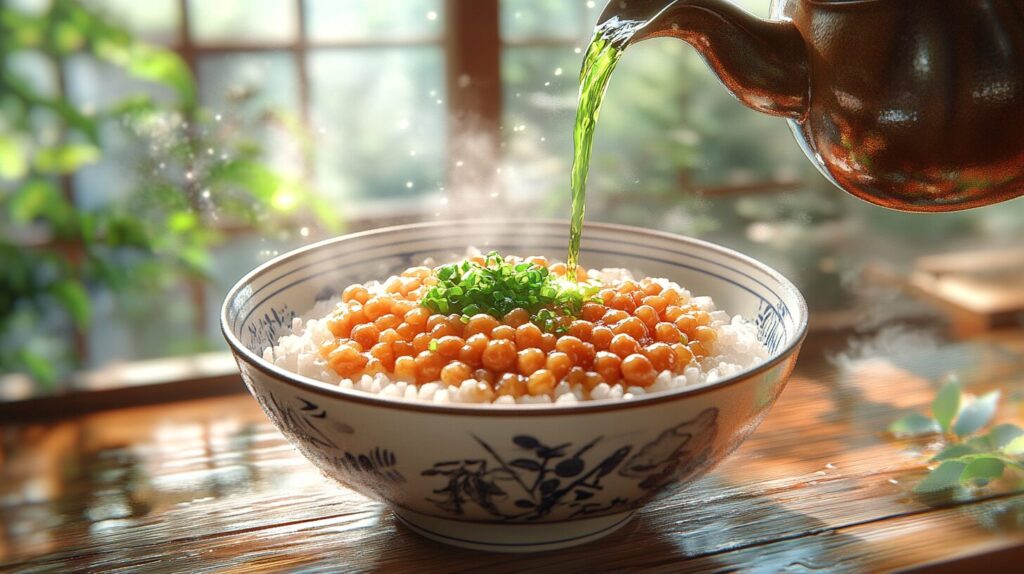
この章では「納豆の茶漬け」のキーとなるシーンをまとめています。
北大路魯山人が納豆の正しい練り方について詳細に説明するシーン。
納豆はまず何も加えずに練り、糸が出れば出すほど美味しくなると説き、醤油は少しずつ加え、決して最初から入れないという拘りを示している。
練り方の一つ一つの工程が美味しさの決め手となる、魯山人の食への真摯な姿勢が表れている場面。
納豆の茶漬けの具体的な作り方を示すシーン。
熱い飯の上に練った納豆を適量のせ、煎茶をかけるという簡素だが奥深い味わいの作り方を説明する。
特に納豆の量は飯の四分の一程度が最適だという繊細な配分感覚が垣間見える。
美味しい納豆と不味い納豆の違いについて解説するシーン。
十分に発酵した良い納豆は糸を引くが、未熟な納豆は糸を引かず「ざくざく」としていると説明。
特に仙台や水戸の小粒納豆を推奨し、魯山人の食材選びの目利きと地方の食文化への造詣の深さを感じさせる場面。
 あおなみ
あおなみ北大路魯山人の随筆「納豆の茶漬け」は、一見シンプルな料理の中に無限の深みを見出す、日本の食文化への敬意と愛情が詰まった作品です。
『納豆の茶漬け』の考察や気づき


「北大路魯山人」が『納豆の茶漬け』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 日常食の芸術化
北大路魯山人は納豆という庶民的な食材を丁寧に扱うことで、日常の食事を芸術に昇華させる姿勢を示しています。単なる食べ物ではなく、その作法や味わい方にまで目を向けることで、日常に潜む美を発見し、それを大切にする日本文化の真髄を伝えています。
魯山人にとって食は単なる栄養摂取ではなく、五感で楽しむ芸術であり、その思想が納豆の茶漬けという一見シンプルな料理の中に凝縮されているのです。 - 調理の哲学
納豆を練る際の細やかな指示には、魯山人の調理に対する哲学が表れています。
手間を惜しまず丁寧に向き合うことで、食材の持つ最大の美味しさを引き出す—この姿勢は料理だけでなく、あらゆる創造的な営みに通じるものです。
魯山人は調理という行為を通して、物事に真摯に向き合う大切さ、プロセスを尊重する精神性を伝えようとしています。 - 食の文化継承
納豆の茶漬けという一見簡素な料理を丁寧に解説することで、魯山人は日本の食文化の奥深さとその継承の重要性を説いています。
地方の名産品への言及や、伝統的な食べ方の紹介には、急速に変化する食文化の中で失われがちな価値を守ろうとする意識が表れています。
魯山人は単なる料理の紹介を超え、日本の食文化全体に対する愛情と敬意を込めて、この作品を書いたのでしょう。



北大路魯山人の「納豆の茶漬け」は、一皿の料理の中に日本文化の精髄を見出す、まさに「食」を通した文化論であり、美学の実践なのです。
北大路魯山人について
北大路魯山人(1883-1959)は、日本を代表する美食家であり、陶芸家、書家、料理人、篆刻家など多彩な才能を持った芸術家です。本名は北大路秀麿。「魯山人」は自らが名乗った雅号です。
「納豆の茶漬け」に見られるように、魯山人は日常的な食材や料理に対しても並々ならぬこだわりを持ち、その本質的な美味しさを追求しました。
彼にとって食は単なる栄養摂取ではなく、五感全てで楽しむべき芸術でした。
この随筆からも、納豆という庶民的な食材に対する深い洞察と敬意が感じられます。
魯山人は1925年に東京・赤坂に「美食倶楽部」を開設し、後に「星岡茶寮」として知られる料亭を営みました。
そこでは自ら料理を考案するだけでなく、料理を盛る器も自作するという、食と器の一体化を実践しました。
「納豆の茶漬け」の随筆にも、料理の味わいだけでなく、その作法や背景にまで言及する魯山人の美意識が表れています。
特に注目すべきは、魯山人が美食を通して日本文化の本質を捉え、表現しようとしたことです。
「納豆の茶漬け」における納豆の練り方や茶漬けの作法の細やかな指示は、日本的な「型」の美学を思わせます。
手間を惜しまず、一つ一つの工程を大切にする姿勢は、日本の伝統的な職人気質と重なります。
また、地方の食材(仙台や水戸の納豆)への言及からは、魯山人の日本各地の食文化に対する広範な知識と愛情も伝わってきます。
彼は全国を旅して各地の食材や料理法を学び、それを自らの料理や芸術に昇華させました。
北大路魯山人は、「食べることは、すなわち芸術である」という信念のもと、生涯にわたって食と芸術の融合を追求し続けた人物です。
この「納豆の茶漬け」という小さな随筆の中にも、そんな魯山人の美学と哲学が凝縮されているのです。
『納豆の茶漬け』のあおなみのひとこと感想



北大路魯山人の「納豆の茶漬け」は、シンプルな料理を芸術に昇華させる魯山人の美意識が光る作品です。
納豆を練る所作から茶漬けの配分まで、細部へのこだわりが食の奥深さを教えてくれます。
日常の中に美を見出す感性と、本物を見極める眼力、そして一見平凡なものの中に無限の味わいを発見する喜びを、魯山人は静かに、しかし確かに伝えています。
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!