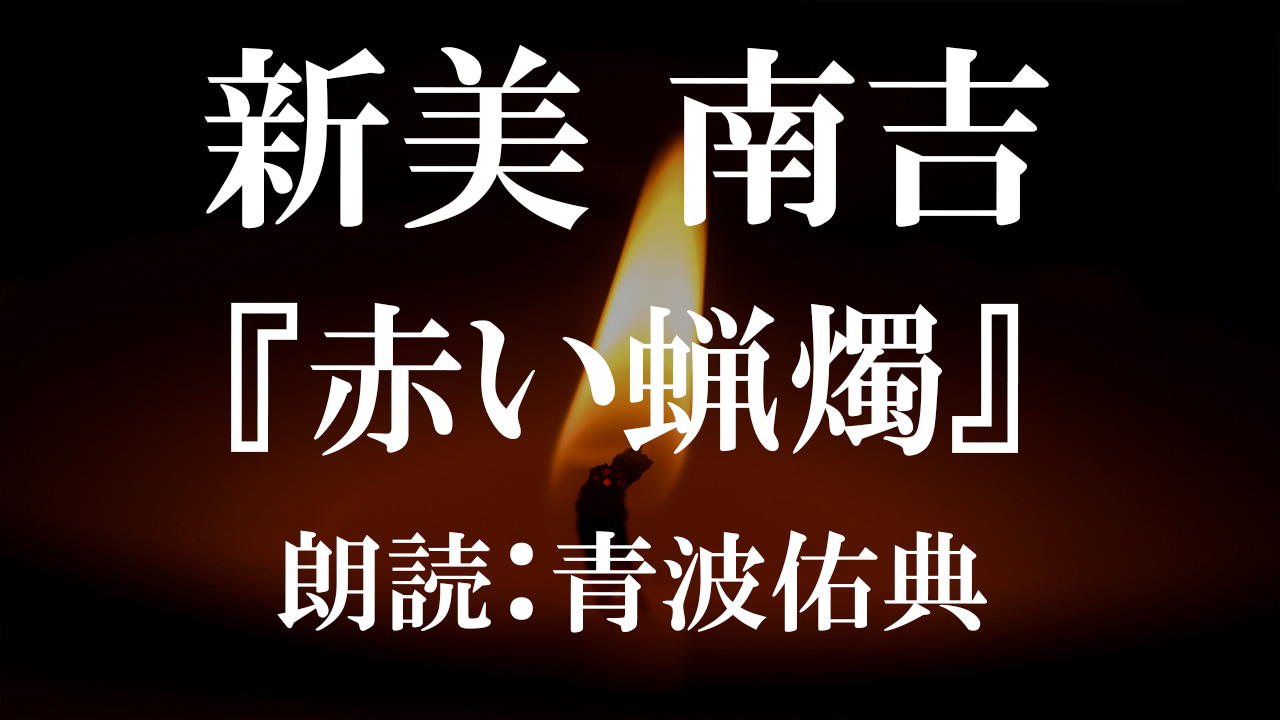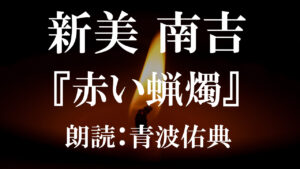「赤い蝋燭」は新美南吉が描く、動物たちの勘違いから生まれる心温まる物語です。
山で拾った赤い蝋燭を「花火」だと思い込んだ猿と、その話に興奮する森の仲間たち。期待と不安が入り混じる中で迎える意外な結末に、思い込みの面白さと人間の心理が映し出されています。
南吉ならではの優しい視点と繊細な描写で綴られたこの童話から、大人も子どもも楽しめる「生きるヒント」を見つけてみませんか?
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『赤い蝋燭』の物語概要とあらすじ
- 『赤い蝋燭』のメッセージや考察
- 『新美南吉』について
『赤い蝋燭』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
山から里へ遊びに行った猿が、赤い蝋燭を拾います。赤い蝋燭はめずらしいものだったため、猿はそれを花火だと思い込んでしまいました。
大切にその「花火」を山に持ち帰った猿は、仲間たちに自慢します。
山では大騒ぎになりました。鹿、猪、兎、亀、鼬、狸、狐など、山の動物たちは誰一人として花火を見たことがなかったからです。
みんなが興味津々で蝋燭を覗き込むと、猿は「危ない!近づいてはいけない。爆発するから」と注意します。
猿は花火がどんなに大きな音を立てて飛び出し、空に美しく広がるかを動物たちに説明しました。
その美しさに魅了された動物たちは、実際に打ち上げてみたいと思うようになります。
そこで、その日の夜に山の頂上で花火を打ち上げることになりました。
夜になり、動物たちは期待に胸を躍らせながら山の頂上に集まります。
猿はすでに赤い蝋燭を木の枝に括り付けて準備を整えていました。
しかし、いざ花火を打ち上げようとすると問題が発生します。誰も火をつける勇気がなかったのです。
くじ引きで火をつける役を決めることになり、最初に亀が選ばれました。しかし亀は蝋燭に近づくと怖くなって首を引っ込めてしまいます。
次に鼬が選ばれましたが、ひどい近眼のため蝋燭の周りをうろつくだけで火をつけられません。
最終的に勇敢な猪が自ら名乗り出て、蝋燭に火をつけることに成功します。
動物たちは爆発を恐れて耳も目もふさぎ、草むらに隠れますが、予想に反して蝋燭は静かに燃えるだけでした。
この物語は、未知のものに対する好奇心と恐れ、そして思い込みによる勘違いをユーモラスに描いています。
動物たちの様子や性格が生き生きと描かれ、猿の思い込みから始まった一連の出来事が読者を楽しませます。
新美南吉特有の優しい視点と明るい語り口で綴られた童話作品です。
主な登場人物
- 猿
山から里へ遊びに行き、赤い蝋燭を拾って花火だと思い込み、他の動物たちに自慢して夜に打ち上げる計画を立てた張本人。 - 亀
花火に火をつけるくじを引いたが、蝋燭に近づくと怖くなって首を引っ込めてしまい、役目を果たせなかった臆病な動物。 - 鼬
二番目に火をつける役を引き当てたが、ひどい近眼のため蝋燭の場所がわからず、周りをうろついているだけで役目を果たせなかった動物。 - 猪
勇敢に自ら進み出て蝋燭に火をつけることに成功した勇気ある動物。
『赤い蝋燭』の重要シーンまとめ

この章では「赤い蝋燭」のキーとなるシーンをまとめています。
山から里へ遊びに行った猿が赤い蝋燭を拾い、それを花火だと勘違いするシーン。物語の発端となり、猿の思い込みが後の展開を生み出します。
猿が「花火」を山に持ち帰り、他の動物たちに見せびらかすシーン。動物たちは花火を見たことがなく大騒ぎになります。猿が「危ない、爆発する」と言うことで緊張感が高まります。
猿が花火の美しさや迫力を動物たちに説明し、みんなが実際に見たいと思うようになるシーン。期待感が高まり、夜に山の頂上で打ち上げる計画が立てられます。
誰も進んで火をつけようとしないため、くじ引きで役割を決めるシーン。危険を恐れる動物たちの心理が表れています。
くじで選ばれた亀が火をつけようとするが、怖くなって首を引っ込めてしまうシーン。亀の臆病な性格が描かれています。
二番目に選ばれた鼬が近眼のために蝋燭の周りをうろつくだけで火をつけられないシーン。鼬の特性が物語に活かされています。
最終的に猪が勇敢に出てきて火をつけることに成功するシーン。猪の勇気が際立ちます。
動物たちが爆発を恐れて隠れる中、蝋燭は静かに燃えるだけという結末。思い込みによる期待と現実のギャップが描かれた作品のクライマックスです。
 あおなみ
あおなみ新美南吉のこの作品は、思い込みと期待、そして未知のものへの恐れと好奇心を動物たちの個性を通して描き、読者に温かな笑いをもたらしています。子どもにも理解しやすい形で人間の心理を映し出した優れた童話です。
『赤い蝋燭』の考察や気づき


「新美南吉」が『赤い蝋燭』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 思い込みの危うさ
新美南吉は「赤い蝋燭」を通して、思い込みがいかに現実を歪めるかを描いています。
猿は単なる蝋燭を花火だと思い込み、その思い込みが他の動物たちにも伝染していきます。
彼らは見たこともない花火の素晴らしさを想像し、大きな期待を抱きますが、結局それは静かに燃える蝋燭に過ぎませんでした。
この作品は、確かな根拠なく物事を判断することの危うさを子どもにも理解できる形で示しています。 - 未知のものへの恐れと好奇心
作品では、動物たちが未知の「花火」に対して恐れと好奇心という相反する感情を抱く様子が描かれています。
彼らは爆発することを恐れながらも、その美しさを見たいという好奇心で頂上に集まります。
新美南吉は、人間が新しいものに出会ったときに感じる両義的な感情を、動物の反応を通して巧みに表現し、未知のものへの向き合い方について考えさせてくれます。 - 個性と協力の大切さ
物語では各動物の特性(亀の臆病さ、鼬の近眼、猪の勇敢さ)が描かれ、最終的に猪の勇気によって蝋燭に火がつきます。
作者は異なる個性を持つ者同士が協力することの重要性を伝えています。
一人では成し遂げられないことも、それぞれの個性を活かし助け合うことで実現できる—そんなメッセージが込められているのではないでしょうか。



新美南吉はシンプルな童話の形を借りながら、人間の心理や社会の縮図を見事に表現しています。「赤い蝋燭」は子どもにも理解できる物語でありながら、大人が読んでも深い示唆に富んだ作品ですね。
新美南吉について
新美南吉(1913-1943)は、昭和初期を代表する童話作家です。
愛知県半田市(当時の知多郡半田町)に生まれ、わずか30歳という若さで結核により亡くなりました。
彼の短い生涯にも関わらず、「ごん狐」「手袋を買いに」「でんでんむしのかなしみ」など、日本の児童文学に大きな足跡を残しています。
「赤い蝋燭」に見られるように、新美南吉の作品には以下のような特徴があります:
- 動物を主人公とした寓話的表現: 「赤い蝋燭」では猿や亀、鼬、猪などの動物たちが登場し、それぞれの性格や特性を通して人間社会の縮図を描いています。南吉は動物を通して人間の本質や社会の仕組みを優しく伝える手法を多くの作品で用いています。
- 純粋さと哀しみの共存: 「赤い蝋燭」はユーモラスな作品ですが、南吉の多くの作品には純粋さと哀しみが共存しています。彼自身が幼くして母を亡くし、継母との確執や病との闘いなど、苦難の多い人生を送ったことが創作に影響していると言われています。
- 優しい視点と細やかな描写: 動物たちの心理や行動を細やかに描写し、読者に温かい共感を呼び起こします。「赤い蝋燭」でも、各動物の個性や反応が生き生きと描かれています。
- 教訓的でありながら押し付けがましくない: 「赤い蝋燭」のように、南吉の作品は単なる教訓話ではなく、読者自身が考えるきっかけを与えてくれます。思い込みの危うさや協力の大切さなどのメッセージが、自然な形で物語に溶け込んでいます。
南吉は教員としても活動しており、子どもたちへの深い愛情を持っていました。
しかし、病気との闘いや経済的な苦境など、決して恵まれた環境ではなかったことが知られています。
そんな中で生み出された彼の作品は、現実の厳しさを知りながらも希望を見出そうとする姿勢が感じられ、今日まで多くの人々に愛され続けているのです。
「赤い蝋燭」に見られる優しいユーモアと動物たちの生き生きとした姿は、短い生涯ながらも豊かな作品世界を築いた新美南吉の才能を示す一例と言えるでしょう。
『赤い蝋燭』のあおなみのひとこと感想



「赤い蝋燭」は、思い込みから始まる小さな冒険を通して、期待と現実のギャップをユーモラスに描いた作品です。
動物たちの個性が生き生きと表現され、読者に温かな微笑みをもたらします。
蝋燭が静かに燃えるだけというシンプルな結末には、新美南吉ならではの優しさと深い洞察が感じられます。
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!