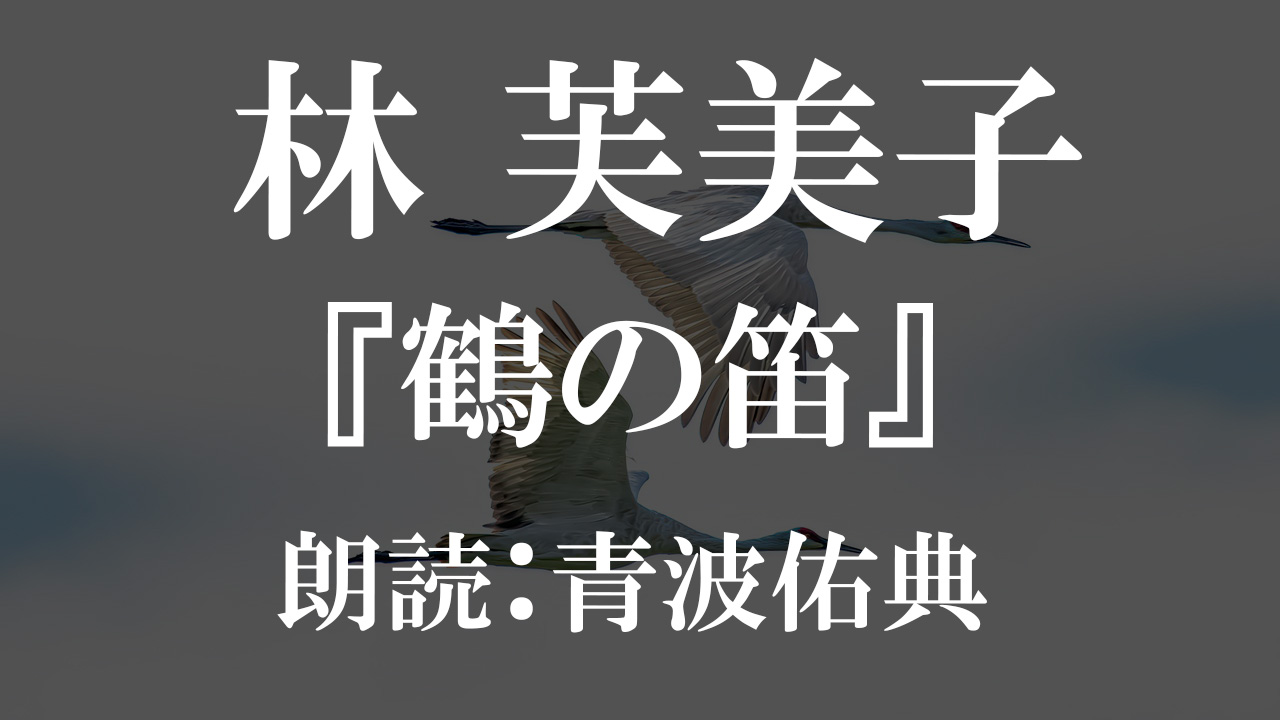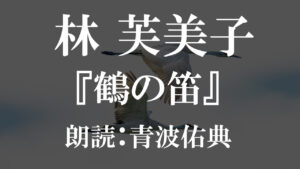心が疲れたとき、ふと耳を澄ませたくなるような、優しく切ない物語があります。
『鶴の笛』は、飢えと孤独に耐える中でも、希望を見失わず助け合って生きる鶴たちの姿を描いた名作。
林芙美子が紡いだ静かな世界に、あなたもそっと触れてみませんか?
\耳から作品を楽しみたい方は、全編を以下YouTubeで朗読しております/
- 『鶴の笛』の物語概要とあらすじ
- 『鶴の笛』のメッセージや考察
- 『林芙美子』について
『鶴の笛』のあらすじと登場人物について

あらすじ
※ネタバレを避けたい方はスキップしましょう!
昔、飢饉が続いたある村に、たくさんの鶴が住んでいました。
食べ物が尽きたため、ほとんどの鶴たちは他の土地へ旅立ってしまいますが、足の悪い鶴とそのお嫁さんだけが村に残りました。
二羽はさびれた沼地で、わずかな食べ物を求めて苦しい生活を送っていました。
ある日、お嫁さんの鶴が食べ物を探していると、どこからともなく美しい笛の音が聞こえてきます。
音の方へ向かうと、それは足の悪い鶴が吹いていた笛でした。
沼の中で偶然見つけた笛を吹いてみたところ、心が落ち着くような美しい音が出たのです。
笛の音色に癒された二羽は、次第に心の中に希望を持つようになり、過去の不満や他の鶴への恨みも忘れていきます。
その後、お嫁さんの鶴は魚の群れを見つけ、帰り道でかつて旅立った鶴の夫婦と再会します。
その夫婦は旅先で子どもを亡くし、悲しみに暮れていたところ、どこからか聞こえた美しい笛の音に導かれて戻ってきたのです。
村に戻った鶴たちは、変わった空気に驚きながらも、お嫁さん鶴の優しさと足の悪い鶴の笛の音に心を打たれます。
そして、みんなで食べ物を分け合い、思いやりと感謝の気持ちを大切にするようになります。
ある夜、月明かりの中で再び笛の音が響くと、次々に昔村を去った鶴たちが帰ってきます。
足の悪い鶴は「誰も威張らずに分け合って暮らせるなら、帰っておいで」と優しく迎え入れました。
こうして村には再び平和が戻り、みんなで協力し合いながら、心豊かに暮らすようになりました。
笛の音はいつも、「きれいな心を忘れずに、貧しくても助け合って生きていこう」と優しく語りかけていたのです。
主な登場人物
- 足の悪い鶴
村に残った雄の鶴で、偶然見つけた笛を吹くことで周囲に希望と安らぎをもたらし、仲間たちの心を変えていく中心的存在。 - お嫁さんの鶴
足の悪い鶴の妻で、苦しい状況の中でも優しさと行動力を持ち、魚を見つけたり他の鶴たちを迎え入れたりして村の再生に貢献する。 - 旅から戻った鶴の夫婦
食糧を求めて村を離れたが、旅先で子どもを失い、笛の音に導かれて帰ってくることで、再び助け合う暮らしの大切さを知る。 - 子どもの鶴たち
旅から戻った夫婦の子どもたちで、帰郷後は穏やかになり、歌をうたうなど平和な村の象徴となる存在。 - 村を去っていた他の鶴たち
飢饉を逃れて村を離れたものの、笛の音に惹かれて次々と帰ってきて、最終的には助け合いの暮らしに参加する。
『鶴の笛』の重要シーンまとめ

この章では「鶴の笛」のキーとなるシーンをまとめています。
足の悪い鶴が沼で偶然笛を見つけ、美しい音色を鳴らすことで、空腹や不満を忘れさせる心の癒しを得る転機となる場面。
お嫁さんの鶴が旅から戻った鶴の家族に再会し、自分たちのわずかな食料を惜しみなく分け与えることで、心の豊かさが広がる場面。
美しい月夜に笛の音が響き、子どもたちが歌い出すことで村に希望と穏やかな時間が戻ったことを象徴する感動的な場面。
かつて村を去った鶴たちが笛の音に導かれて次々と帰ってきて、助け合いの気持ちを取り戻す象徴的なクライマックス。
すべての鶴が力を合わせて働き、食べ物を分かち合いながら心豊かに暮らしていくという新しい生き方が根づいた結末の場面。
 あおなみ
あおなみ小さな笛が、大きな心の変化を生んだ物語です。
『鶴の笛』の考察や気づき


「林芙美子」が『鶴の笛』を通して伝えたかったメッセージを、以下のように考察しました。
- 思いやりの力
飢えと苦しみの中でも、他者を思いやる心があれば人は優しくなれるということを、鶴たちの変化を通して描いている。 - 心の豊かさの大切さ
物質的な貧しさがあっても、心が満たされていれば幸せになれるという、内面の豊かさの価値を伝えようとしている。 - 本当の幸せとは
自分だけの幸せを求めるより、みんなと分かち合い支え合うことが、真の幸せにつながるというメッセージが込められている。



静かな物語の中に、力強い希望が光っていますね。
林芙美子について
林芙美子という作家
林芙美子(はやし・ふみこ)は、1903年に生まれ、戦前・戦後を代表する日本の女性作家の一人です。
彼女自身、極貧の幼少期を過ごし、職を転々としながら苦しい生活を体験しました。代表作に『放浪記』がありますが、それも彼女の貧しく孤独な放浪生活を元にした自伝的作品です。
貧しさを超える“心の強さ”
『鶴の笛』には、貧しさの中でも希望や思いやりを忘れずに生きる姿が描かれています。
これは林芙美子自身の生き様と重なります。彼女も困難な時代を「心」で生き抜いた人物であり、「心が貧しくなければ、人は豊かになれる」という信念が物語にも通じています。
静けさと強さの共存
林芙美子の作品は、派手なドラマよりも、小さな日常の中にある静かな感情や強い意志を丁寧に描くのが特徴です。
『鶴の笛』も、笛の音という静けさの中に、鶴たちが変わっていく“希望”や“優しさ”が込められており、彼女らしいタッチが光ります。
“分かち合い”へのまなざし
物語で描かれる「助け合い」「分け合い」は、戦争や貧困の中で人がどう生きるかを常に見つめ続けてきた林芙美子の視点です。彼女は、文学の中で社会の厳しさと、人間のあたたかさの両方を描こうとしていました。
子どもへの優しいまなざし
『鶴の笛』は、児童文学のようなやさしい語り口ですが、その中に人生の真実があります。
林芙美子は、子どもにも「生きることの大切さ」「思いやり」の本質を伝えたいという気持ちで、このような作品を遺したのかもしれません。
どんなに貧しくても、心に希望と優しさを持っていれば、人生は美しくなる——林芙美子が伝えたかったことは、今を生きる私たちにも、やさしく、まっすぐに響いてきます。
『鶴の笛』のあおなみのひとこと感想



『鶴の笛』は、苦しみの中でも思いやりを忘れずに生きる大切さを教えてくれる温かな物語でした。
笛の音に導かれて変わっていく鶴たちの姿が、希望や優しさの力を静かに語りかけてきます。心がほっとする一編です。
日本ブログ村に参加してます^^
↓クリックしてくれると嬉しいです!